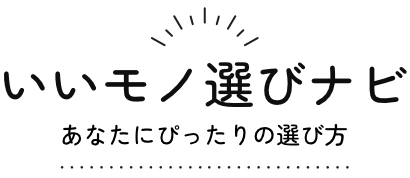愛犬が体を掻き続ける姿、見ていて辛いですよね。
そのしつこいかゆみ、もしかしたら毎日のドッグフードが原因の食物アレルギーかもしれません。
この記事では、犬の皮膚トラブルとアレルギーの基礎知識から、カイカイ対策に繋がるドッグフードの選び方の具体的なポイントまで、飼い主目線で分かりやすく解説します。
フードの見直しで、愛犬のつらい皮膚のかゆみを和らげるヒントを見つけませんか。
はじめに:愛犬の「カイカイ」、もしかしてドッグフードが原因?
愛犬が体を掻いたり、同じ場所をずーっと舐めたり、噛んだり…。
そんな姿を見ていると、「かゆいのかな?痛いのかな?」と、こっちまでなんだか辛くなってしまいますよね。
特に、夜中にポリポリ掻く音で目が覚めてしまったり、皮膚が赤くなっているのを見つけたりすると、何かできることはないかと必死に考えてしまうものです。
もちろん、かゆみの原因は色々考えられますが、もしシャンプーを変えても、お薬を塗ってもなかなか治らないとしたら…。
もしかすると、そのしつこい「カイカイ」の原因は、意外なところにあるのかもしれません。
その「カイカイ」、毎日の食事が関係しているかも
実は、犬のかゆみや皮膚トラブルの原因として、毎日の食事が大きく関係しているケースが少なくない、という話をよく耳にします。
私たち人間も、体質に合わないものを食べると肌が荒れたりすることがありますよね。
それと同じで、犬も毎日食べているドッグフードに含まれる何らかの成分が、体の内側からかゆみを引き起こしている可能性があるんです。
「うちの子、最近よく体を掻いているな」と感じたら、一度フードのパッケージの裏側をじっくりと見てみるのが、カイカイ対策の第一歩になるかもしれません。
食物アレルギーって何?原因から対策までを解説
「アレルギー」という言葉はよく聞きますが、一体どういう仕組みでかゆみが起きるのでしょうか。
すごく簡単に言うと、体を守るはずの免疫システムが、特定の食べ物を「敵だ!」と勘違いして、過剰に攻撃してしまう反応のことだと言われています。
その攻撃のサインとして、皮膚にかゆみや赤みといった症状が現れることがあるんですね。
この記事では、そんなドッグフードとアレルギーの関係に焦点を当てて、飼い主として何ができるのか、フード選びのヒントなどを一緒に考えていきたいと思います。
あくまで飼い主目線のヒントとして
ここで一つだけお伝えしておきたいのは、この記事は獣医師のような専門家が書いているわけではない、ということです。
あくまで、一人の愛犬家として集めた情報や、よく言われている話を元に、「こんな視点もあるよ」というヒントをお伝えするものです。
なので、医学的な判断や診断はできません。
愛犬の症状がひどい場合や、心配なことがある場合は、必ずかかりつけの動物病院に相談してくださいね。
それを踏まえた上で、読み進めていただけると嬉しいです。
この記事でわかること
この記事では、犬の食物アレルギーの基本的な知識から、アレルギーを考慮したドッグフードの選び方の具体的なポイント、そしてフード以外の原因や日常でできるケアまで、幅広く解説していきます。
この記事を読み終わる頃には、愛犬のカイカイに対して、飼い主としてどんなアプローチができるのか、その選択肢がきっと見えているはずです。
愛犬のかゆみを少しでも和らげてあげるために、一緒に学んでいきましょう。
これってアレルギー?犬の皮膚トラブルと食物アレルギーの基礎知識

愛犬のカイカイの原因を探るために、まずは「食物アレルギー」について、もう少しだけ詳しくなってみましょう。
「アレルギー」という言葉は知っていても、どうして起こるのか、どんな症状があるのか、意外と知らないことも多いかもしれません。
ここでは、食物アレルギーの基本的な知識を、分かりやすく解説していきます。
なぜアレルギー反応が起きるの?そのメカニズム
そもそも、どうして特定の食べ物でアレルギー反応が起きてしまうのでしょうか。
私たちの体には、外から入ってきたウイルスや細菌などの敵と戦う「免疫」というシステムが備わっています。
食物アレルギーは、この免疫システムが、本来は無害であるはずの食べ物に含まれるタンパク質を「敵だ!」と間違えて認識し、攻撃を始めてしまうことで起こる、と言われています。
一度「敵」だと記憶されると、次に同じ食べ物が入ってきた時にも、ヒスタミンなどの化学物質を放出して体を守ろうとします。
このヒスタミンが、皮膚の血管を広げたり、神経を刺激したりすることで、「かゆみ」や「赤み」といった症状を引き起こすと考えられているんですね。
かゆみだけじゃない!食物アレルギーで見られる症状
食物アレルギーの症状は、かゆみだけではありません。
もし、愛犬に以下のようなサインが見られたら、もしかしたら食べ物が関係しているかもしれません。
いくつか代表的なものを挙げてみますね。
皮膚の赤みやブツブツ
かゆみと合わせて、皮膚が赤くなったり、小さなブツブツができていたりすることがあります。
特に、耳の付け根、目の周り、口の周り、脇の下、お腹、足先など、皮膚の柔らかい部分に出やすい傾向があるようです。
掻きすぎて、じゅくじゅくしてしまったり、逆にかさぶたになったりすることもあります。
脱毛・毛が薄くなる
同じ場所を繰り返し掻いたり、舐めたりすることで、その部分の毛が薄くなったり、抜けてしまったりすることがあります。
特に、足先をずっと舐め続けて、毛の色が赤茶色に変色している場合は、アレルギーのサインかもしれません。
しきりに体を家具にこすりつけている、なんて行動も注意して見てあげたいですね。
下痢や嘔吐などの消化器症状
アレルギー反応は、皮膚だけでなく、消化器官に現れることもあります。
フードを変えてから、なんだかウンチがゆるくなった、吐く回数が増えた、といった場合は、そのフードが体に合っていない可能性があります。
皮膚の症状と合わせて、お腹の調子もチェックしてあげることが大切だと思います。
外耳炎を繰り返す
耳の中が赤く腫れたり、匂いの強い耳垢がたくさん出たりする「外耳炎」。
これを何度も繰り返す場合も、食物アレルギーが隠れていることがある、という話をよく耳にします。
耳のケアをしっかりしているのに、すぐにまた耳を痒がる、頭を振る、といった仕草が見られたら、一度食事を疑ってみるのも良いかもしれません。
犬のアレルゲンになりやすいと言われる食材リスト
では、具体的にどんな食材がアレルギーの原因になりやすいのでしょうか。
一般的に、犬のアレルゲンになりやすいと言われている食材には、以下のようなものがあります。
もちろん、どの食材に反応するかは、その子の体質によって全く違うので、あくまで参考として見てくださいね。
– 牛肉
– 乳製品(牛乳、チーズなど)
– 鶏肉
– 鶏卵
– 小麦
– 大豆
– ラム肉
– トウモロコシ
意外なことに、良質なタンパク質源だと思っていたお肉類も、アレルゲンになる可能性があるんですね。
今までたくさん食べてきた食材ほど、アレルギーを発症しやすい、とも言われているようです。
食物アレルギーと食物不耐性の違いって?
アレルギーとよく似た言葉に、「食物不耐性」というものがあります。
これは、免疫システムが関わるアレルギーとは違って、特定の食材をうまく消化・吸収できない体質のことです。
例えば、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする「乳糖不耐症」などがこれにあたります。
症状としては、下痢や嘔吐といった消化器系のトラブルが主で、アレルギーのような激しいかゆみを伴うことは少ないと言われています。
原因となる仕組みは違いますが、どちらも特定の食べ物が体に合わない、という点では同じですね。
正確な診断は動物病院で
ここまで色々な症状を挙げてきましたが、これらの症状は、食物アレルギー以外の病気でも見られることがあります。
例えば、アトピー性皮膚炎や、ノミ・ダニのアレルギー、細菌感染など、原因は様々です。
「うちの子、アレルギーかも?」と思っても、自己判断で食事を極端に制限したりするのは危険です。
まずは、かかりつけの動物病院で獣医師さんに相談し、適切な検査や診断を受けることが、カイカイ解決への一番の近道だと思います。
カイカイ対策の第一歩!アレルギーを考慮したドッグフードの選び方

愛犬の食物アレルギーの可能性が見えてきたら、次はいよいよフード選びの実践編です。
世の中にはたくさんのドッグフードがあって、「うちの子にはどれがいいの?」と迷ってしまいますよね。
でも、大丈夫です。
アレルギーを考慮したフード選びには、いくつか分かりやすいポイントがあります。
ここでは、カイカイ対策の第一歩として、フードのパッケージ裏を見ながらチェックしたい5つのポイントを、優先順位の高いものからご紹介していきます。
ポイント1:主原料のタンパク質をチェック【最重要】
食物アレルギー対策のフード選びで、最も重要だと言われているのが、主原料となる「タンパク質」の種類です。
アレルギーは、今まで食べてきたタンパク質に対して反応することが多い、という話をしましたよね。
なので、アレルギーを疑う場合は、その原因となっているタンパク質を突き止めて、それを避けることが基本になります。
今まで食べたことのない「新規タンパク質」を試す
カイカイ対策としてよく行われるのが、今まで愛犬が食べたことのない、新しい種類のタンパク質(新規タンパク質)を使ったフードを試してみる方法です。
例えば、今までチキンやビーフがメインのフードを食べていたなら、鹿肉(ベニソン)や魚、馬肉、カンガルーといった、ちょっと珍しいお肉が主原料のフードを選んでみる、という感じです。
体がまだ「敵」として認識していないタンパク質なので、アレルギー反応が起きにくい、という考え方ですね。
アレルゲンを細かく分解した「加水分解タンパク質」
もう一つの選択肢として、「加水分解タンパク質」を使ったフードがあります。
これは、アレルギーの原因になりやすいタンパク質を、あらかじめ酵素などを使って非常に細かーく分解しておくことで、免疫システムに「敵だ!」と気づかれにくくする、という特殊な製法で作られたタンパク質です。
主に、動物病院で処方される療法食などで使われていることが多いですね。
アレルゲンが特定できない場合や、複数の食材にアレルギーがある場合などに、獣医師さんから勧められることがあるかもしれません。
ポイント2:穀物の使用をチェック(グレインフリー)
犬のアレルゲンになりやすい食材として、小麦やトウモロコシといった穀物を挙げました。
犬はもともと肉食寄りの動物なので、穀物の消化があまり得意ではない、と言われています。
そのため、消化の際に体に負担がかかりやすく、アレルギーの原因になることも。
最近では、これらの穀物を一切使わない「グレインフリー」のドッグフードがたくさん販売されています。
もし、今あげているフードの原材料に、小麦やトウモロコシがたくさん含まれているようなら、一度グレインフリーのフードを試してみる価値はあると思います。
ポイント3:原材料の種類が少ない「限定原材料フード」
アレルギーの原因を探る上で、とても有効なのが「LID(Limited Ingredient Diets)」、日本語で言うと「限定原材料フード」です。
これは、その名の通り、使われている原材料の種類をできるだけ少なく、シンプルに作られているフードのこと。
例えば、「主原料はラム肉だけで、炭水化物源はサツマイモだけ」というように、タンパク質源と炭水化物源がそれぞれ1〜2種類に絞られています。
原材料が少ないと、もしアレルギー症状が出た場合に、「原因はこの食材かも」と特定しやすくなるんですね。
アレルギー体質の子の、原因究明の第一歩として、とても理にかなったフードだと思います。
ポイント4:皮膚の健康をサポートする成分に注目
フードを選ぶ際には、皮膚の健康をサポートしてくれる成分が含まれているかどうかも、ぜひチェックしたいポイントです。
例えば、オメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸といった必須脂肪酸は、皮膚のバリア機能を健康に保ち、炎症を抑える働きがあると言われています。
サーモンオイルや亜麻仁油などに多く含まれていますね。
また、亜鉛やビタミン類も、健康な皮膚や被毛を維持するためには欠かせない栄養素です。
アレルギー対策と合わせて、こういった皮膚のケアを考えた成分が配合されているフードを選ぶと、より効果が期待できるかもしれません。
ポイント5:人工的な添加物はなるべく避ける
着色料や香料、合成の酸化防止剤といった人工的な添加物も、犬の体にとっては負担になり、アレルギーのような反応を引き起こす原因になることがある、と言われています。
特に、皮膚がデリケートになっている時は、できるだけ体に優しい、シンプルなフードを選んであげたいですよね。
フードの色をカラフルにするための着色料は、犬にとっては全く必要のないものです。
原材料表示をよく見て、ローズマリー抽出物など、天然由来の成分で品質を保っている、無添加のフードを選ぶことを心がけると、より安心だと思います。
フードだけじゃない!かゆみの原因と日常でできるスキンケア
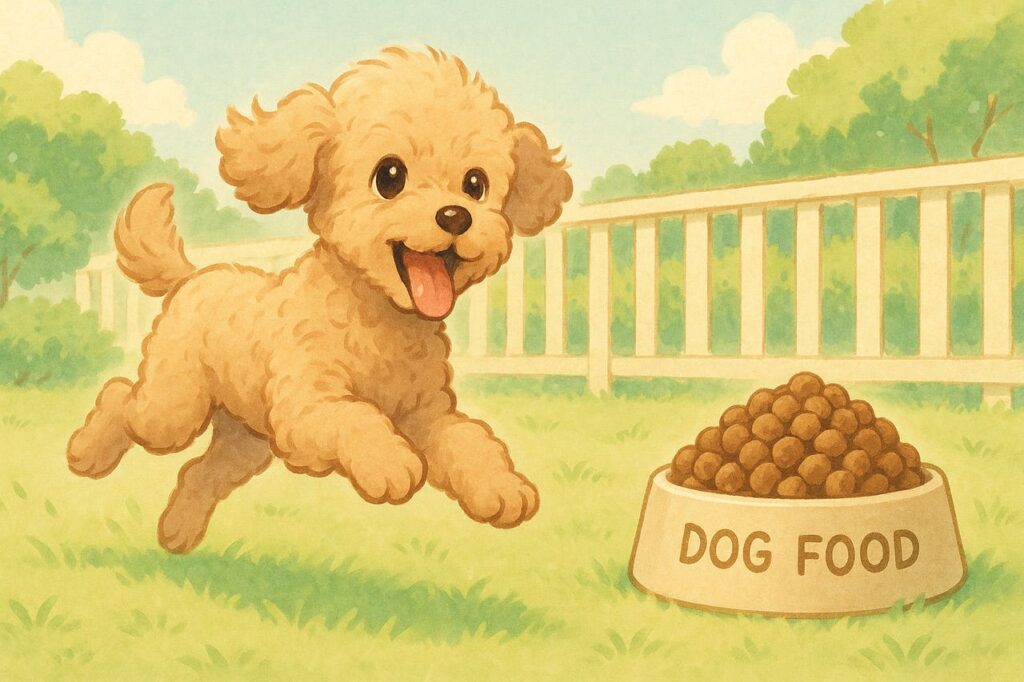
ドッグフードを見直すことは、カイカイ対策の大きな柱です。
でも、愛犬のかゆみの原因は、食べ物だけとは限りません。
「フードを変えたのに、まだ痒がっている…」という場合は、食べ物以外の原因にも目を向けてみる必要があります。
ここでは、食物アレルギー以外に考えられるかゆみの原因と、お家でできる日常的なスキンケアについてお話しします。
内側からのケアと外側からのケア、両方からアプローチしていくことが、カイカイ卒業への近道だと思います。
食物以外のアレルギー(アトピー性皮膚炎など)
愛犬のカイカイの原因は、食べ物だけとは限りません。
実は、犬のかゆみの原因として非常に多いのが、「アトピー性皮膚炎」だと言われています。
これは、ハウスダストや花粉、カビなど、環境の中にあるアレルゲンに対して、免疫が過剰に反応してしまうことで起こる皮膚炎です。
特定の季節になると症状が悪化する、足先や顔、お腹などを特によく痒がる、といった特徴が見られることが多いようです。
食物アレルギーと併発しているケースも少なくないので、フードを見直しても改善しない場合は、環境アレルギーの可能性も考えてみたいですね。
ノミ・ダニなどの外部寄生虫
ノミやマダニが体に寄生することでも、激しいかゆみを引き起こします。
特に、ノミの唾液に対してアレルギー反応を起こす「ノミアレルギー性皮膚炎」は、腰のあたりに強いかゆみや湿疹が出るのが特徴的です。
お散歩の際に草むらでくっついてきたり、他の犬からうつったりすることもあります。
動物病院で処方される駆除薬で、定期的にしっかりと予防してあげることが、何よりの対策になります。
毎月の予防を忘れないようにしたいですね。
乾燥や不適切なシャンプーによる皮膚トラブル
私たち人間も、空気が乾燥する冬は肌がカサカサしてかゆくなりますよね。
犬も同じで、皮膚が乾燥するとバリア機能が低下して、外部からの刺激に弱くなり、かゆみが出やすくなります。
また、良かれと思ってやっているシャンプーが、逆効果になっていることも。
洗浄力の強すぎるシャンプーを使ったり、頻繁に洗いすぎたりすると、皮膚を守るために必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥を招いてしまいます。
シャンプーは、犬用の低刺激なものを選び、適切な頻度で行うことが大切だと思います。
ストレスが原因で体を舐め壊してしまうことも
意外な原因として、ストレスもあります。
お留守番の時間が長かったり、運動不足だったり、家族とのコミュニケーションが足りなかったりすると、犬は不安や退屈を感じてしまいます。
その気持ちを紛わすために、自分の足先やしっぽなどを、ずーっと舐め続けてしまうことがあるんです。
これを「舐性皮膚炎(しせいひふえん)」と言って、舐め壊した部分が炎症を起こし、さらに気になって舐める…という悪循環に陥ってしまうことも。
愛犬との時間を見直し、心を満たしてあげることも、カイカイ対策の一つなんですね。
ブラッシングや保湿など、お家でできるスキンケア
カイカイ対策として、お家でできるスキンケアもたくさんあります。
毎日のブラッシングは、皮膚の血行を良くし、抜け毛やフケを取り除くことで、皮膚を清潔に保つ効果が期待できます。
愛犬とのコミュニケーションの時間にもなりますし、皮膚の異常を早期発見することにも繋がりますね。
また、皮膚の乾燥が気になる場合は、犬用の保湿スプレーや保湿ローションを使って、潤いを補ってあげるのも良い方法です。
シャンプーの後に保湿してあげるだけでも、乾燥のしやすさが全然違う、という話をよく聞きます。
できることから、少しずつ取り入れていきたいですね。
これってアレルギー?犬の皮膚トラブルと食物アレルギーの基礎知識

愛犬のカイカイの原因を探るために、まずは「食物アレルギー」について、もう少しだけ詳しくなってみましょう。
「アレルギー」という言葉は知っていても、どうして起こるのか、どんな症状があるのか、意外と知らないことも多いかもしれません。
ここでは、食物アレルギーの基本的な知識を、分かりやすく解説していきます。
この知識が、フード選びや愛犬の体調管理にきっと役立つはずです。
原因を知ることで、対策も立てやすくなりますからね。
なぜアレルギー反応が起きるの?そのメカニズム
そもそも、どうして特定の食べ物でアレルギー反応が起きてしまうのでしょうか。
私たちの体には、外から入ってきたウイルスや細菌などの敵と戦う「免疫」というシステムが備わっています。
食物アレルギーは、この免疫システムが、本来は無害であるはずの食べ物に含まれるタンパク質を「敵だ!」と間違えて認識し、攻撃を始めてしまうことで起こる、と言われています。
一度「敵」だと記憶されると、次に同じ食べ物が入ってきた時にも、ヒスタミンなどの化学物質を放出して体を守ろうとします。
このヒスタミンが、皮膚の血管を広げたり、神経を刺激したりすることで、「かゆみ」や「赤み」といった症状を引き起こすと考えられているんですね。
かゆみだけじゃない!食物アレルギーで見られる症状
食物アレルギーの症状は、かゆみだけではありません。
もし、愛犬に以下のようなサインが見られたら、もしかしたら食べ物が関係しているかもしれません。
いくつか代表的なものを挙げてみますね。
皮膚の赤みやブツブツ
かゆみと合わせて、皮膚が赤くなったり、小さなブツブツができていたりすることがあります。
特に、耳の付け根、目の周り、口の周り、脇の下、お腹、足先など、皮膚の柔らかい部分に出やすい傾向があるようです。
掻きすぎて、じゅくじゅくしてしまったり、逆にかさぶたになったりすることもあります。
脱毛・毛が薄くなる
同じ場所を繰り返し掻いたり、舐めたりすることで、その部分の毛が薄くなったり、抜けてしまったりすることがあります。
特に、足先をずっと舐め続けて、毛の色が赤茶色に変色している場合は、アレルギーのサインかもしれません。
しきりに体を家具にこすりつけている、なんて行動も注意して見てあげたいですね。
下痢や嘔吐などの消化器症状
アレルギー反応は、皮膚だけでなく、消化器官に現れることもあります。
フードを変えてから、なんだかウンチがゆるくなった、吐く回数が増えた、といった場合は、そのフードが体に合っていない可能性があります。
皮膚の症状と合わせて、お腹の調子もチェックしてあげることが大切だと思います。
外耳炎を繰り返す
耳の中が赤く腫れたり、匂いの強い耳垢がたくさん出たりする「外耳炎」。
これを何度も繰り返す場合も、食物アレルギーが隠れていることがある、という話をよく耳にします。
耳のケアをしっかりしているのに、すぐにまた耳を痒がる、頭を振る、といった仕草が見られたら、一度食事を疑ってみるのも良いかもしれません。
犬のアレルゲンになりやすいと言われる食材リスト
では、具体的にどんな食材がアレルギーの原因になりやすいのでしょうか。
一般的に、犬のアレルゲンになりやすいと言われている食材には、以下のようなものがあります。
もちろん、どの食材に反応するかは、その子の体質によって全く違うので、あくまで参考として見てくださいね。
– 牛肉
– 乳製品(牛乳、チーズなど)
– 鶏肉
– 鶏卵
– 小麦
– 大豆
– ラム肉
– トウモロコシ
意外なことに、良質なタンパク質源だと思っていたお肉類も、アレルゲンになる可能性があるんですね。
今までたくさん食べてきた食材ほど、アレルギーを発症しやすい、とも言われているようです。
食物アレルギーと食物不耐性の違いって?
アレルギーとよく似た言葉に、「食物不耐性」というものがあります。
これは、免疫システムが関わるアレルギーとは違って、特定の食材をうまく消化・吸収できない体質のことです。
例えば、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする「乳糖不耐症」などがこれにあたります。
症状としては、下痢や嘔吐といった消化器系のトラブルが主で、アレルギーのような激しいかゆみを伴うことは少ないと言われています。
原因となる仕組みは違いますが、どちらも特定の食べ物が体に合わない、という点では同じですね。
正確な診断は動物病院で
ここまで色々な症状を挙げてきましたが、これらの症状は、食物アレルギー以外の病気でも見られることがあります。
例えば、アトピー性皮膚炎や、ノミ・ダニのアレルギー、細菌感染など、原因は様々です。
「うちの子、アレルギーかも?」と思っても、自己判断で食事を極端に制限したりするのは危険です。
まずは、かかりつけの動物病院で獣医師さんに相談し、適切な検査や診断を受けることが、カイカイ解決への一番の近道だと思います。
カイカイ対策の第一歩!アレルギーを考慮したドッグフードの選び方

愛犬の食物アレルギーの可能性が見えてきたら、次はいよいよフード選びの実践編です。
世の中にはたくさんのドッグフードがあって、「うちの子にはどれがいいの?」と迷ってしまいますよね。
でも、大丈夫です。
アレルギーを考慮したフード選びには、いくつか分かりやすいポイントがあります。
ここでは、カイカイ対策の第一歩として、フードのパッケージ裏を見ながらチェックしたい5つのポイントを、優先順位の高いものからご紹介していきます。
ポイント1:主原料のタンパク質をチェック【最重要】
食物アレルギー対策のフード選びで、最も重要だと言われているのが、主原料となる「タンパク質」の種類です。
アレルギーは、今まで食べてきたタンパク質に対して反応することが多い、という話をしましたよね。
なので、アレルギーを疑う場合は、その原因となっているタンパク質を突き止めて、それを避けることが基本になります。
今まで食べたことのない「新規タンパク質」を試す
カイカイ対策としてよく行われるのが、今まで愛犬が食べたことのない、新しい種類のタンパク質(新規タンパク質)を使ったフードを試してみる方法です。
例えば、今までチキンやビーフがメインのフードを食べていたなら、鹿肉(ベニソン)や魚、馬肉、カンガルーといった、ちょっと珍しいお肉が主原料のフードを選んでみる、という感じです。
体がまだ「敵」として認識していないタンパク質なので、アレルギー反応が起きにくい、という考え方ですね。
アレルゲンを細かく分解した「加水分解タンパク質」
もう一つの選択肢として、「加水分解タンパク質」を使ったフードがあります。
これは、アレルギーの原因になりやすいタンパク質を、あらかじめ酵素などを使って非常に細かーく分解しておくことで、免疫システムに「敵だ!」と気づかれにくくする、という特殊な製法で作られたタンパク質です。
主に、動物病院で処方される療法食などで使われていることが多いですね。
アレルゲンが特定できない場合や、複数の食材にアレルギーがある場合などに、獣医師さんから勧められることがあるかもしれません。
ポイント2:穀物の使用をチェック(グレインフリー)
犬のアレルゲンになりやすい食材として、小麦やトウモロコシといった穀物を挙げました。
犬はもともと肉食寄りの動物なので、穀物の消化があまり得意ではない、と言われています。
そのため、消化の際に体に負担がかかりやすく、アレルギーの原因になることも。
最近では、これらの穀物を一切使わない「グレインフリー」のドッグフードがたくさん販売されています。
もし、今あげているフードの原材料に、小麦やトウモロコシがたくさん含まれているようなら、一度グレインフリーのフードを試してみる価値はあると思います。
ポイント3:原材料の種類が少ない「限定原材料フード」
アレルギーの原因を探る上で、とても有効なのが「LID(Limited Ingredient Diets)」、日本語で言うと「限定原材料フード」です。
これは、その名の通り、使われている原材料の種類をできるだけ少なく、シンプルに作られているフードのこと。
例えば、「主原料はラム肉だけで、炭水化物源はサツマイモだけ」というように、タンパク質源と炭水化物源がそれぞれ1〜2種類に絞られています。
原材料が少ないと、もしアレルギー症状が出た場合に、「原因はこの食材かも」と特定しやすくなるんですね。
アレルギー体質の子の、原因究明の第一歩として、とても理にかなったフードだと思います。
ポイント4:皮膚の健康をサポートする成分に注目
フードを選ぶ際には、皮膚の健康をサポートしてくれる成分が含まれているかどうかも、ぜひチェックしたいポイントです。
例えば、オメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸といった必須脂肪酸は、皮膚のバリア機能を健康に保ち、炎症を抑える働きがあると言われています。
サーモンオイルや亜麻仁油などに多く含まれていますね。
また、亜鉛やビタミン類も、健康な皮膚や被毛を維持するためには欠かせない栄養素です。
アレルギー対策と合わせて、こういった皮膚のケアを考えた成分が配合されているフードを選ぶと、より効果が期待できるかもしれません。
ポイント5:人工的な添加物はなるべく避ける
着色料や香料、合成の酸化防止剤といった人工的な添加物も、犬の体にとっては負担になり、アレルギーのような反応を引き起こす原因になることがある、と言われています。
特に、皮膚がデリケートになっている時は、できるだけ体に優しい、シンプルなフードを選んであげたいですよね。
フードの色をカラフルにするための着色料は、犬にとっては全く必要のないものです。
原材料表示をよく見て、ローズマリー抽出物など、天然由来の成分で品質を保っている、無添加のフードを選ぶことを心がけると、より安心だと思います。
【Q&A】ドッグフードのアレルギー、よくある質問

フード選びや日常のケアについてお話ししてきましたが、それでも「こういう場合はどうなの?」という細かい疑問は尽きないものですよね。
ここでは、ドッグフードとアレルギーに関して、飼い主さんからよくいただく質問にQ&A形式でお答えしていきます。
Q. アレルギー検査はした方がいい?
A. 原因を特定する一つの有効な手段だと思います。
動物病院では、血液を採取して調べるアレルギー検査(IgE検査)などが行われています。
この検査で、愛犬がどんな食材にアレルギー反応を示しやすいか、その傾向を知ることができます。
ただし、検査結果がすべてではない、という声もよく聞きます。
検査で陽性反応が出た食材でも、実際に食べても症状が出ないこともあれば、逆に陰性だったのに症状が出ることも。
あくまで一つの指標として考え、最終的には実際にフードを与えてみて、愛犬の様子を観察して判断することが大切だと思います。
検査を受けるかどうかは、費用もかかることなので、かかりつけの獣医師さんとよく相談してみてくださいね。
Q. フードを切り替える時の注意点は?
A. お腹をびっくりさせないように、1週間から10日ほどかけてゆっくり切り替えるのがおすすめです。
アレルギー対策で新しいフードを試す時、いきなり全量を新しいフードに変えてしまうと、胃腸が慣れずに下痢や嘔吐をしてしまうことがあります。
これでは、アレルギーによる症状なのか、フードが急に変わったことによる不調なのか、見分けがつきにくくなってしまいます。
初日は今までのフードに新しいフードを1割程度混ぜることから始め、毎日少しずつ新しいフードの割合を増やしていく、という方法が一般的です。
愛犬のウンチの状態などをよく見ながら、焦らずに進めてあげましょう。
Q. 子犬でも食物アレルギーになる?
A. はい、子犬でも食物アレルギーを発症することはあります。
アレルギーは、特定のタンパク質を繰り返し食べることで発症しやすくなると言われているので、成犬になってから発症するイメージが強いかもしれません。
ですが、生まれつきの体質によっては、早い段階で症状が出る子もいるようです。
特に、生後半年から1歳くらいまでの間に、体を痒がったり、お腹の調子が悪かったりといったサインが見られる場合は、一度食事内容を振り返ってみる必要があるかもしれません。
成長期の大切な時期なので、自己判断でフードを制限せず、まずは獣医師さんに相談することが大切です。
Q. アレルギー対応フードは美味しくないって本当?
A. そんなことはないと思いますよ。
昔は、療法食というと「美味しくない」というイメージがあったかもしれませんが、最近のアレルギー対応フードは、食いつきにもこだわって作られているものがたくさんあります。
特に、鹿肉や魚といった新規タンパク質を使ったフードは、犬にとって目新しくて美味しい香りがするので、むしろ喜んで食べる子も多いという話をよく聞きます。
原材料を限定している分、素材そのものの風味が引き立っているのかもしれませんね。
もし食いつきが心配な場合は、少量のお試しパックなどから始めて、愛犬の反応を見てみるのがおすすめです。
【参考】アレルギー対応におすすめのプレミアムドッグフードとは?

アレルギー対策のフード選びのポイントを5つご紹介しましたが、「その条件に合うフードを、たくさんの中から探すのは大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。
そんな時に、フード選びの候補として知っておくと便利なのが、原材料にこだわって作られた「プレミアムドッグフード」です。
なぜプレミアムフードがアレルギー対策になるの?
プレミアムドッグフードが、アレルギー対策としてよく名前が挙がるのには、ちゃんとした理由があります。
それは、これまでお話ししてきた「新規タンパク質の使用」「グレインフリー」「限定された原材料」「不要な添加物不使用」といった、アレルギー対策で重視したいポイントをクリアしている商品が多いからです。
消化しやすい原材料にこだわり、犬の体に余計な負担をかけないように作られているため、アレルギー反応のリスクを低減することが期待できる、というわけなんですね。
アレルギー対策で評価の高いフードの例
「具体的にどんなフードがあるの?」と気になりますよね。
アレルギーに悩む飼い主さんから、「これを試したらカイカイが落ち着いた」という声が聞かれるフードを、参考までにいくつかご紹介します。
モグワン
主原料にチキンとサーモンを使用し、犬の食欲をそそる自然な香りが特徴です。
グレインフリー(穀物不使用)で、原材料の種類も比較的シンプルなので、アレルゲンの特定や除去をしたい場合に試しやすいフードだと思います。
カナガン
こちらもグレインフリーで、主原料はチキンです。
もし愛犬がチキンアレルギーでなければ、皮膚の健康をサポートするオメガ脂肪酸も含まれており、カイカイ対策として人気があります。
もしチキンが合わない場合は、同じシリーズでサーモンを主原料にしたタイプもありますよ。
他にも、鹿肉や魚など、様々な新規タンパク質を使ったプレミアムフードがたくさんあります。
大切なのは「愛犬に合うか」を見極めること
いくつか具体的なフードを挙げましたが、一番大切なことをお伝えします。
それは、どんなに評判が良いフードでも、「最終的に、あなたの愛犬の体に合うかどうかが全て」だということです。
犬にも人間と同じように個性や体質があります。
Aちゃんにはすごく良かったフードが、Bくんには合わない、なんてことは日常茶飯事です。
価格や口コミだけで判断せず、まずはお試しサイズの少量パックなどを活用して、愛犬のウンチの状態や毛並み、そして何より「カイカイ」の様子をしっかり観察しながら、その子にとってのベストなフードを見つけてあげてくださいね。
まとめ:ドッグフードの見直しで、愛犬のカイカイ対策を始めよう
今回は、見ているのも辛い愛犬のしつこい「カイカイ」の原因として、ドッグフードとの関係性に焦点を当ててお話ししてきました。
愛犬のかゆみの原因は一つではありませんが、毎日の食事が体質に合わず、アレルギー反応を引き起こしている可能性は十分に考えられます。
まずは、かゆみ以外にも皮膚の赤みや脱毛、お腹の不調といったサインがないか、愛犬の様子をよく観察してあげましょう。
その上で、カイカイ対策としてドッグフードを見直す際は、
1. 主原料のタンパク質の種類(新規タンパク質など)
2. 穀物不使用(グレインフリー)
3. 原材料の種類が少ない(限定原材料)
4. 皮膚の健康をサポートする成分
5. 不要な人工添加物の有無
といった5つのポイントを意識して選んでみてください。
もちろん、かゆみの原因は食べ物だけでなく、ハウスダストなどの環境アレルギーや、ノミ・ダニ、ストレスなど多岐にわたります。
フードの見直しと並行して、ブラッシングや保湿といった日常のスキンケアも大切です。
何よりも、飼い主さんが一人で抱え込まず、心配な時は必ず動物病院に相談することが解決への一番の近道です。
この記事を参考に、まずはできること、フードの原材料表示をチェックすることから、愛犬のカイカイ対策を始めてみてはいかがでしょうか。