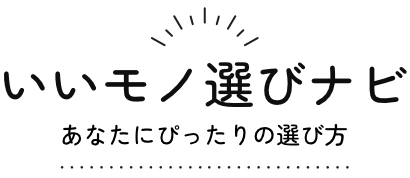愛犬のために、ドッグフードのパッケージに書かれた給与量を参考にしているけれど、「これで本当に合っているのかな?」と不安に感じていませんか?私もそうでした。運動量の多い日や、愛犬の体重が少し増え始めた時など、パッケージの数字だけでは心配になりますよね。
実は、パッケージの給与量はあくまで「標準的な犬」を想定した目安でしかなく、あなたの愛犬の活動量や体質、年齢までは考慮されていません。
ここでは、愛犬の健康を守るために欠かせない、ドッグフードの「本当の適正量」を導き出す計算方法を完全マスターできます。
具体的には、獣医師も使うRER(安静時エネルギー要求量)とDER(一日あたりの必要カロリー)の計算式を使い、愛犬の状況に合わせた正確な給与量(g数)を知る手順を解説します。
この記事を読めば、もうパッケージの目安に頼る必要はありません。愛犬の健康をコントロールする食事量の管理スキルを身につけて、健やかな毎日をサポートしていきましょう。
ドッグフードのパッケージ記載量が「目安」でしかない理由を知ろう
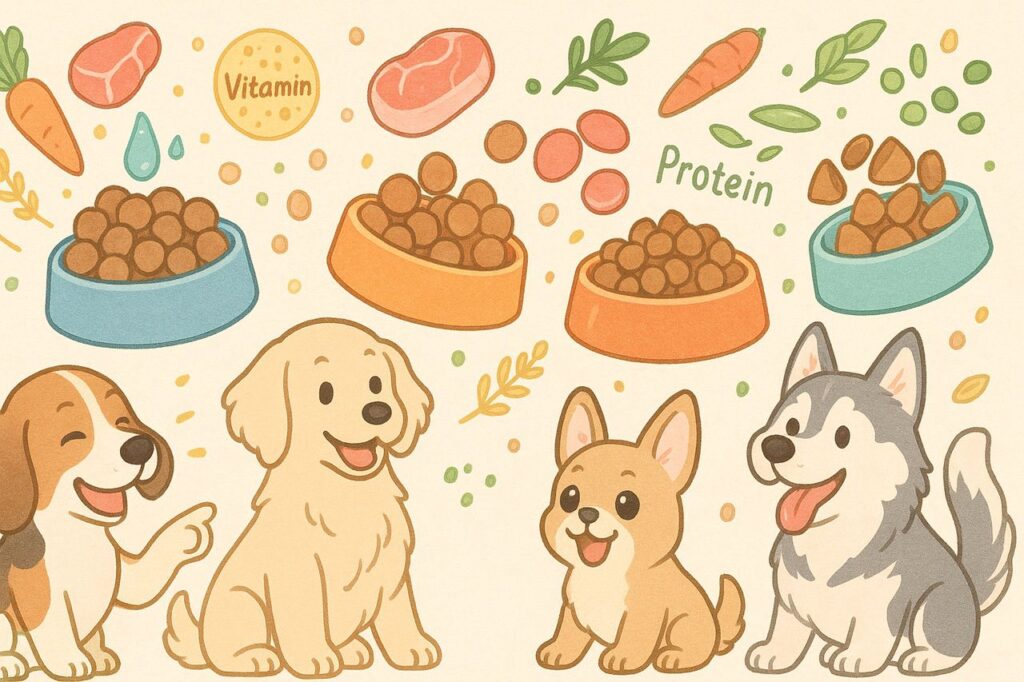
愛犬のために、ドッグフードのパッケージに記載されている給与量を参考にしている飼い主さんは多いですよね。私も新しいフードに切り替える際は、まずその記載量を見てしまいます。
でも、その数字が愛犬にとって「完璧な答え」ではないということをご存知でしょうか?
ここでは、なぜパッケージの記載量が目安でしかないのか、そして愛犬の健康を守るために一歩踏み込んで、適正量を知ることがいかに大切かを見ていきましょう。
正直なところ、この適正量の把握こそが、愛犬の健康管理の土台を築くことにつながると思っています。
給与量が表示されるパッケージの「計算基準」とは?
ドッグフードのパッケージに載っている給与量は、決して適当に決められているわけではありません。ほとんどの場合、AAFCO(全米飼料検査官協会)などの栄養基準に基づき、「平均的な体型の成犬」や「一般的な活動量」を想定して計算されています。
つまり、静かな室内で穏やかに過ごす犬を想定した、いわば「標準モデル」の犬を基準にしていることが多いんです。
これは、フードメーカーとして栄養基準を満たすための「最低限の量」や「一般的な量」を示すものであり、あなたの愛犬の特別な状況までは考慮されていない、ということを理解しておく必要があります。
パッケージの目安では不十分!「愛犬の個性」を考慮すべき理由
私たち人間と同じように、犬も一頭一頭、体質や生活スタイルが大きく異なりますよね。
パッケージの目安だけでフードを与え続けるのが危険なのは、この愛犬の個性が考慮されていないからです。
例えば、毎日ドッグランで活発に走り回る犬と、ほとんど散歩に行かない犬では、消費するエネルギーが全く違います。また、去勢・避妊手術をしている犬は、代謝が低下して太りやすくなるとも言われています。
愛犬の「年齢(代謝の違い)」「犬種」「一日の運動量」といった個体差を無視してパッケージ通りに与えてしまうと、カロリー過多で肥満になったり、逆に活動量が多い子は栄養不足になったりするリスクがあるんですよ。
愛犬の適正量を知る上で欠かせない「3つの重要な要素」
では、パッケージの目安に頼らず、愛犬の真の適正量を知るにはどうしたらいいのでしょうか?
実は、次の3つの要素がわかれば、正確な給与量を計算することができます。
一つ目は、愛犬の「理想体重」です。現在の体重が適正でない場合、目標とする健康的な体重を基準にする必要があります。
二つ目は、愛犬の「活動レベル」です。一日の運動量によって、必要なエネルギー(カロリー)は大きく変わってきます。
そして三つ目が、「ドッグフードのカロリー密度」です。与えているフード100gあたり、あるいは1粒あたりに何kcal含まれているか、という情報ですね。これはパッケージに必ず記載されているので確認しましょう。
次の章では、これらの要素を使って、愛犬に必要なカロリーを導き出す具体的な計算方法を解説していきます。
ドッグフードの量が多すぎる・少なすぎると起こる健康問題
適正量を知ることの重要性は、愛犬の健康問題の予防に直結するからです。
量が多すぎる場合、最も多いのは肥満です。肥満は、糖尿病や心臓病、関節炎などの様々な病気を引き起こす要因になると言われています。膝や腰に負担がかかるのも見ていて辛いですよね。
逆に量が少なすぎると、成長期の子犬は発育不良になったり、シニア犬は体温調節が難しくなったり、免疫力が低下したりといったリスクが生じます。
愛犬の今の状態を維持するのではなく、「より健やかに過ごす」ために、給与量を調整する意識を持ちたいものですね。
あなたの愛犬は痩せすぎ?肥満?「ボディコンディションスコア(BCS)」の測り方
愛犬の体重が適正かどうかを客観的に判断するために、獣医師も使用する「ボディコンディションスコア(BCS)」という指標を活用しましょう。
BCSは1から9までの9段階で評価され、理想的な体型は「4」または「5」とされています。このBCSを測ることで、現在の体重が理想体重とどれだけ離れているかが判断できますよ。
チェックポイントは主に3つです。
1. 肋骨: 触って簡単に確認できる(BCS4〜5)、または軽く触れるだけで確認できる(BCS6以上は確認しにくい)。
2. 腰のくびれ: 真上から見たときに、くびれがはっきりしているか、していないか。
3. 腹部のたるみ: 横から見たときに、お腹が引き締まって上向きに上がっているか(タックアップ)どうか。
まずはご自身の手で愛犬を触って、現在のBCSを把握してみることから始めてみませんか。
【実践】愛犬の「本当の適正量」を計算する2ステップ
前の章で愛犬のBCS(体型)を確認できたなら、いよいよ本題の給与量計算に進みましょう。愛犬の「本当の適正量」を知るためには、「カロリー計算」を行うのが最も確実で科学的な方法だとされています。
計算というと難しそうに聞こえるかもしれませんが、手順はたったの2ステップです。ここでは、獣医師も用いるRER(安静時エネルギー要求量)とDER(一日あたりの必要カロリー)という指標を使って、あなたの愛犬に必要なカロリーを正確に導き出していきます。
私も最初はこの計算に驚きましたが、一度計算してしまえば、フード選びや調整が格段にしやすくなると思いますよ。
ステップ1:安静時エネルギー要求量(RER)を計算する
まず、最初に行うのはRER(Resting Energy Requirement:安静時エネルギー要求量)の計算です。
これは、愛犬が一日中寝て過ごしていても、心臓を動かしたり呼吸をしたりといった、生命を維持するために最低限必要なエネルギー(カロリー)のことです。
RERの計算には、次の式を使います。
\[RER (kcal) = ext{体重}^{0.75} imes 70\]
RER計算式と、愛犬の「理想体重」の決め方
この計算式で重要なのは、体重の部分に、現在の体重ではなく「愛犬の理想体重」を使うという点です。もし現在の愛犬が肥満傾向(BCS6以上)であれば、その体重のまま計算するとカロリーを摂りすぎてしまうからです。
愛犬の理想体重が分からない場合は、獣医師に相談するのが一番確実です。
暫定的な目安として、もし愛犬が肥満であれば、現在の体重から10%〜20%ほど減らした値を理想体重として設定し、そこから計算を始めてみるのも一つの方法だと思います。
計算は面倒?RERの早見表(体重別)を活用しよう
「体重の0.75乗なんて、計算機がないと無理!」と思われる方も多いですよね。私もそう思います。そこで、体重別のRERの目安を早見表にまとめました。まずはここから愛犬のRERの目安を把握してみましょう。
| 愛犬の体重(kg) | RER(安静時エネルギー要求量)の目安(kcal) |
|---|---|
| 5 kg | 275 kcal |
| 10 kg | 450 kcal |
| 15 kg | 608 kcal |
| 20 kg | 757 kcal |
| 25 kg | 899 kcal |
あくまで目安ですが、このRERが、愛犬の食事量を決めるための「土台」になります。
ステップ2:活動量・年齢に応じた係数でDER(一日あたりの必要カロリー)を計算する
RERがわかったら、次にDER(Daily Energy Requirement:一日あたりの必要カロリー)を計算します。
DERは、RERに、愛犬の「活動量」「年齢」「去勢・避妊の有無」といった個別の状況を考慮した「活動係数(K値)」をかけて算出します。これが、愛犬の本当の適正量を知るための最も重要な調整ポイントになります。
\[DER (kcal) = RER (kcal) imes ext{活動係数(K値)}\]
DER計算に必要な「活動係数」の具体的な目安
愛犬の状況によって、活動係数は以下のような目安が設定されています。
| 愛犬の状況 | 活動係数(K値)の目安 |
|---|---|
| 減量が必要な肥満犬 | 1.0 〜 1.4 |
| 避妊・去勢手術済みの成犬(一般的な活動量) | 1.6 |
| 未去勢・未避妊の成犬(一般的な活動量) | 1.8 |
| 体重維持のための活動量の多い犬 | 2.0 〜 5.0 |
| 子犬(生後4ヶ月以降) | 2.0 〜 3.0 |
減量や極端に活動量が多い犬の場合は、この係数が大きく変動します。特に減量を目指す場合は、自己判断せず、獣医師と相談しながら係数を決めることを強くおすすめします。
活動係数を使って、愛犬の一日の必要カロリーを算出
例えば、「体重10kg(理想体重)で、避妊・去勢手術済みの成犬」の場合を計算してみましょう。
RER(早見表より): 約450 kcal
活動係数(K値): 1.6
DER (kcal) = 450 kcal × 1.6 = 720 kcal
この愛犬の場合、一日に必要なカロリーは720 kcalということがわかります。このDERこそが、あなたの愛犬の「本当の適正カロリー」なんですよ。
一日の必要カロリーからドッグフードの「g数」を導き出す方法
最後に、計算で導き出したDER(一日の必要カロリー)を使って、実際に与えるドッグフードの「g数」に変換します。
この計算には、ドッグフードのカロリー密度の情報が必要です。これはパッケージの裏側などに「代謝エネルギー(ME)〇〇kcal/100g」といった形で記載されています。
計算式は非常にシンプルです。
\[ ext{一日の給与量} (g) = rac{ ext{DER} (kcal)}{ ext{フードのカロリー密度} (kcal/g)}\]
もしフードに「350 kcal/100g」と記載されていた場合、カロリー密度は「3.5 kcal/g」となります。
先ほどの例(DER 720 kcal)に当てはめると、720 kcal ÷ 3.5 kcal/g = 約205.7 gが、一日に与えるべきフードの適正量となります。
この計算結果とパッケージの目安量を比較すると、思っていたよりも量が少なかったり、多かったりすることに気づくかもしれませんね。
愛犬の状況別!ドッグフードの量を調整する際の注意点

前の章で愛犬のDER(一日の必要カロリー)を計算しましたが、その計算結果はあくまで「基礎」です。愛犬の年齢や健康状態によって、必要なエネルギー量は日々変動しているんですよ。
特に、「子犬」「シニア犬」、そして「肥満犬」は、成犬とは異なる食事量と配慮が必要になります。これらの状況に合わせた給与量の調整方法と、その際の注意点を詳しく見ていきましょう。
この微調整こそが、愛犬の体調を安定させ、病気を未然に防ぐ重要な鍵を握っていると私は思います。
子犬の場合:成長曲線と体重増加に合わせた食事量調整
子犬は、体をどんどん作る「成長期」にあるため、成犬と比べて体重あたりのエネルギー要求量が非常に高いです。一般的に、成犬の約2倍から3倍のカロリーが必要になると言われています。
ただし、この高いエネルギー要求量は、成長のピークである生後4〜5ヶ月頃を境に、徐々に低下していきます。
このため、子犬への給与量を決める際は、計算で出した値を固定するのではなく、愛犬の成長曲線と体重増加に合わせて、段階的に量を調整していくことが大切です。
月齢ごとの成長期に必要なエネルギー量の違い
子犬の成長に伴い、必要なエネルギーを示す活動係数は以下のように変化していきます。
生後4ヶ月までは非常に高く、その後は徐々に減っていきます。特に成長期が終わる目安である1歳頃に、子犬用フードから成犬用フードへ切り替えるタイミングで、給与量も成犬の係数(約1.6〜1.8)に合わせて大きく減らす必要があります。
このタイミングを見誤ると、体が成熟しきっていないのにカロリー過多になり、若いうちから肥満傾向になってしまうことがあるので注意が必要ですね。
子犬の食事回数と一日の食事量バランスの取り方
子犬の胃はまだ小さく、一度に大量のフードを消化するのは負担になります。そのため、一日の総給与量を守りつつ、食事の回数を増やして少量ずつ与えることが重要です。
一般的には、生後3ヶ月頃までは一日に3回から4回に分けて与え、生後6ヶ月を過ぎたら2回から3回に減らしていくのがおすすめです。
食事回数を分けて与えることで、消化器への負担が減るだけでなく、血糖値の急激な上昇を防ぎ、安定したエネルギー供給につながるとされています。
シニア犬の場合:代謝の低下と活動量に合わせた食事量調整
シニア犬は、子犬とは真逆で、加齢に伴い代謝が低下し、活動量が減少するため、必要なカロリーはぐっと減ります。
成犬の活動係数(1.6〜1.8)に対し、シニア犬は1.4〜1.6程度の、より低い係数で計算されることが多いです。
しかし、カロリーは減らしても、健康を維持するために必要なタンパク質やビタミン、ミネラルといった栄養素の「質」は落とせません。むしろ、消化吸収を助ける高品質な栄養素がこれまで以上に重要になってきます。
シニア期におけるカロリーコントロールの重要性
シニア犬が肥満になると、衰え始めた関節や心臓に大きな負担がかかり、生活の質を大きく下げてしまいます。
そのため、シニア期に入ったら、計算で出したDERを参考に、定期的にBCSをチェックし、体重が微増したらすぐ食事量を微調整する機敏な対応が大切です。
ただ、食欲の低下や病気で体重が減ってしまう場合は、逆にカロリーを増やさなければなりません。この時期の体重管理は非常にデリケートなので、極端な制限を自己判断で行わず、必ず獣医師と相談しながら進めてくださいね。
シニア犬が食欲不振の時にカロリーを確保する工夫
病気や老化で食欲が落ちてしまったシニア犬に対し、必要なカロリーを確保するのは飼い主の大きな課題ですよね。
少量でも効率よくカロリーを摂らせるために、高カロリーの栄養補助食品や、嗜好性の高いウェットフードを普段のフードに混ぜて使うといった工夫が有効です。
また、食事の回数を増やしたり、フードを少し温めて香りを立たせる(前の記事でも紹介しましたね)といった配慮も、食欲を刺激する助けになりますよ。
ダイエットが必要な肥満犬の食事量と目標設定
現在の愛犬が肥満(BCS6以上)でダイエットが必要な場合、計算に用いる活動係数を1.0〜1.4という低い値に設定して、食事量を制限することから始めます。
この際、いきなり大幅に制限するのは絶対に避けるべきです。急激なダイエットは愛犬にストレスを与えるだけでなく、健康を損なう原因にもなります。
目標は、数ヶ月かけてゆっくりと理想体重を達成することです。獣医師と相談して具体的な減量計画と目標体重(理想体重)を決め、その目標体重を基準に計算したRERの1.0〜1.4倍のカロリーを、まずは試してみるのが良いでしょう。
食事の量を減らすだけでなく、散歩の時間を増やす、一緒に遊ぶ時間を設けるなど、消費カロリーを増やす工夫も忘れずに行ってあげたいですね。
愛犬の健康維持をサポートする「ドッグフードの賢い選び方」3つの視点
愛犬に必要なカロリー(DER)と、そこから導かれる正確な給与量(g数)を計算で把握することができましたね。しかし、その「量」を与えるドッグフード自体が愛犬に合っていなければ、せっかくの努力も水の泡になってしまうかもしれません。
ここでは、給与量の計算を実践したあなたが、さらに一歩進んだ健康管理を行うために、フードを選ぶ際にチェックしてほしい3つの視点を解説します。
この視点は、特に体重管理や健康維持を目的とする場合に、非常に役立つと思います。
視点1:正確な給与量計算に役立つ「カロリー表記」の明確さ
前の章で、最終的な給与量(g)を出すには、フードのカロリー密度(kcal/g)が必要だと解説しましたよね。そのため、まず選ぶべきフードは、カロリー表記が明確に記載されているものです。
パッケージの裏側などに「代謝エネルギー(ME)〇〇kcal/100g」といった形で、正確な数値が示されているかを確認しましょう。
「このドッグフード、なんだか良さそう!」と感じても、このカロリー表記が曖昧だと、せっかく計算したDERを正確なg数に変換することができなくなってしまいます。
正確な給与管理を行いたいなら、カロリー表記が明確なフードを選ぶことが、最初の賢い選択だと私は思います。
視点2:ダイエットや体重維持に重要な「タンパク質と脂質のバランス」
計算で導き出したDERのカロリーを、どのような栄養素から摂取するかが、愛犬の健康維持を左右します。
特に、ダイエットが必要な犬や、代謝が落ちるシニア犬の体重維持を目指す場合は、「タンパク質と脂質のバランス」が非常に重要になります。
高タンパク質・低脂質なフードを選ぶのが理想的です。タンパク質は筋肉の維持を助け、代謝をサポートする働きが期待できると言われています。
一方で、脂質はエネルギー密度が非常に高いため、脂質が多いフードは必然的にカロリー密度も高くなります。同じg数を与えても、脂質の多いフードではカロリーオーバーになりがちなので、パッケージの成分表をしっかり比較検討してくださいね。
視点3:食事量の調整がしやすい「粒の大きさや密度」の比較
計算で「一日に200g与える」と決まっても、粒の大きさや密度(硬さ)によって、愛犬が食べる「カサ(物理的な量)」は大きく変わります。
例えば、ダイエット中で食事の総量が少なくなり、愛犬に「なんか物足りないな…」と感じさせてしまうのが心配な場合。
粒が大きく、比較的密度が低いフードの方が、同じg数でも食器に入れた時にかさが増し、愛犬が視覚的・体感的に満足感を得やすいというメリットがあります。
逆に、食欲不振のシニア犬や、たくさん食べられない子犬の場合は、少量で効率よくカロリーを摂らせるために、粒が小さく、カロリー密度が高いフードを選ぶ方が適しているかもしれません。
愛犬の性格や食欲に合わせて、フードの「粒の形状」も給与量調整の視点として見てみるのはいかがでしょうか。
【計算後の実践へ】カロリー調整しやすい「人気ドッグフード」徹底比較
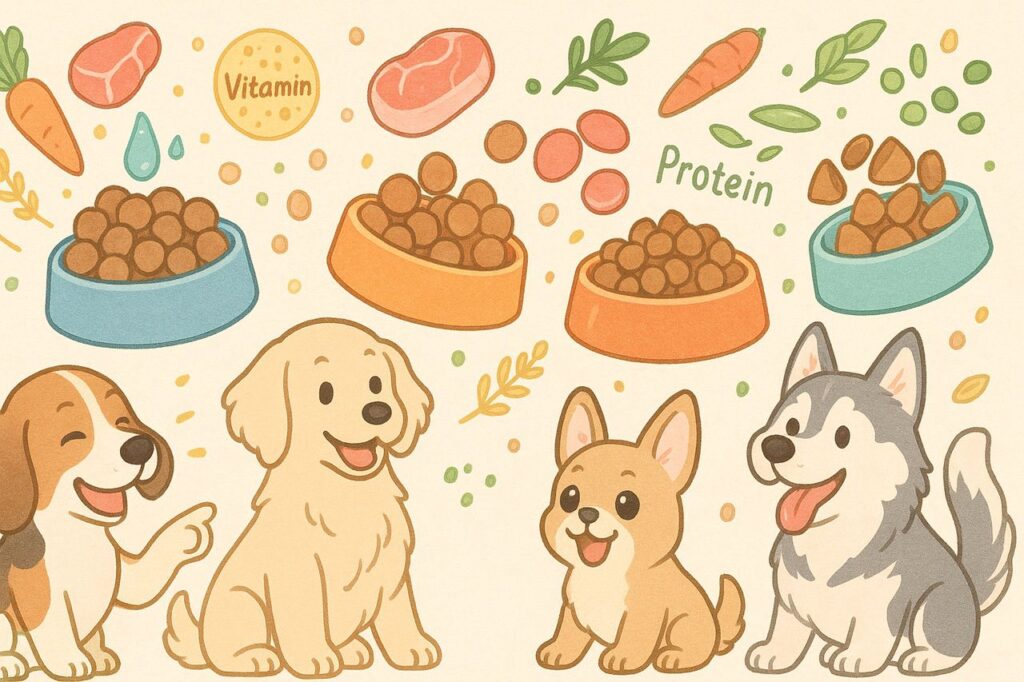
愛犬のDER(一日あたりの必要カロリー)と、そこから導かれる正確な給与量(g数)がわかると、「よし、この量を与えるのに最適なフードはどれだろう?」と具体的な商品選びに進みたくなりますよね。
ここでは、前の章で解説したカロリー調整や栄養バランスの視点を踏まえ、特に給与量管理がしやすいと評判の高いドッグフードをいくつかピックアップしてご紹介します。
計算で導き出した数字を無駄にしないためにも、フード選びは慎重に行いたいものです。
ダイエット・体重維持におすすめの人気ドッグフードの特徴比較
「うちの子、ちょっと太り気味で…」とダイエットが必要な場合や、代謝が落ちたシニア犬の体重維持には、高タンパク質・低脂質で、カロリー密度が低めに抑えられたフードが適しています。
例えば、獣医師の指導のもとで使われることが多い「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット r/d」や「ロイヤルカナン ベッツプラン ウェイトケア」といった療法食や準療法食は、その設計が非常に優れています。
これらのフードは、満腹感を持続させるために食物繊維が豊富に含まれていることが多く、高タンパク質で筋肉を維持しながら、低カロリーで脂肪を減らすというダイエットの基本を忠実にサポートしてくれます。
特に、カロリー密度が明確なので、計算で出したDERから正確な給与量を導き出しやすいのも、大きなメリットだと思います。
運動量が多い愛犬におすすめの高カロリーフードの特徴比較
逆に、運動量が非常に多いアスリート犬や、病気などで食欲が落ちて少量しか食べられない愛犬には、高カロリー密度のフードが適しています。
この場合、計算で導き出した高いDERを満たすために、フードの量を増やしすぎると胃に負担がかかってしまう可能性があります。そのため、少量で多くのカロリーを摂取できるフードが理想的です。
例えば、原材料の質にこだわった「オリジン オリジナル」や「アカナ パシフィカ」など、動物性タンパク質と良質な脂質が豊富に含まれたフードは、効率的にエネルギーを供給するのに向いています。
ただし、これらはカロリーが高いため、運動量が少ない犬に与えるとすぐにカロリーオーバーになるので、愛犬の活動レベルを正確に把握して選んでくださいね。
人気フードの比較早見表:カロリー・栄養素
ここで、給与量調整の視点でいくつかのフードの目安を比較してみましょう。ご自身の愛犬のDERと比較する際の参考にしてください。
| ドッグフード名 | 目的の目安 | カロリー密度(kcal/100g) | タンパク質/脂質比率 | 給与量調整のしやすさ |
|---|---|---|---|---|
| ヒルズ r/d | 減量(ダイエット) | 約300以下 | 高タンパク/超低脂質 | 獣医師指導で細かな調整が可能 |
| ロイヤルカナン ウェイトケア | 体重維持/減量サポート | 約300〜350 | 高タンパク/低脂質 | カロリー明確で計算しやすい |
| オリジン オリジナル | 高活動量/高栄養 | 約400以上 | 高タンパク/高脂質 | 少量で高カロリーを確保できる |
※カロリーはフードの種類や国によって変動することがあります。必ずお手元のパッケージを確認してください。
正確な給与量を与えるための「計量アイテム」のススメ
せっかくDERを正確に計算し、「一日に205g」といったg数を導き出しても、計量が正確でなければ意味がありませんよね。パッケージに付属しているカップや、一般的な計量カップで測ると、フードの詰め方次第で簡単に10%以上の誤差が出てしまうことがあります。
そこでおすすめしたいのが、デジタルスケール(デジタル秤)の活用です。
1g単位で正確に測れるデジタルスケールを使えば、計算で出したg数をそのまま正確に愛犬に与えることができます。これが、カロリーコントロールを成功させるための、最後の、そして最も重要なステップだと私は思います。
フードの保存容器に、デジタルスケールで測ったグラム数をメモして貼っておくなど、日々の管理を簡単にする工夫を取り入れてみてくださいね。
愛犬の適正量をマスターして健やかな毎日を送ろう(まとめ)
ドッグフードのパッケージに書かれた給与量は、あくまで「平均的な犬」を想定した目安でしかないことを理解いただけたかと思います。
愛犬の健康を守るためには、安静時エネルギー要求量(RER)と一日あたりの必要カロリー(DER)を計算し、愛犬の理想体重や活動レベルに合わせて給与量(g数)を正確に導き出すことが不可欠です。
この計算方法は、少し手間がかかるかもしれませんが、一度マスターすれば、子犬の成長やシニア犬の代謝の低下、ダイエットの必要がある時など、どんな状況でも自信を持って食事量を調整できるようになりますよ。
そして、計算で導き出した適正量を、カロリー表記が明確で、愛犬の体質に合った高品質なフードで与えてあげることが、愛犬の健やかな毎日を守るための最も重要な土台になるはずです。ぜひ、今日から愛犬のBCSをチェックしながら、食事量管理を実践してみてくださいね。
愛犬の食事に関する、こちらの記事も読んでみませんか?
愛犬の適正量(DER)を計算できるようになれば、愛犬の健康管理はもうプロ級です。しかし、愛犬の食事に関する悩みは、「量」だけではありません。
食事の質をさらに高めるための「トッピング」の工夫や、フードの品質を守る「保存方法」、そして新しいフードへの「切り替え方」といった、給与量管理と密接に関わるテーマを扱った記事も用意しています。
ぜひ、この機会に、愛犬の食事全般に関する知識を深め、万全な体制で健やかな毎日をサポートしていきましょう。
関連記事一覧
- いつものごはんに一工夫!愛犬が喜ぶ「ちょい足し」トッピングアイデア集計算で出した適正量を守りながら、マンネリしがちな毎日の食事を豊かに。栄養バランスを崩さずに、愛犬の食欲をそそる簡単なトッピングのアイデアを食材別に紹介します。
 いつものごはんに一工夫!愛犬が喜ぶ「ちょい足し」トッピングアイデア集いつものドッグフードに飽きていませんか。愛犬の食事のマンネリを解消する、簡単なドッグフードトッピングのアイデアをご紹介します。栄養バランスを考えた手作りレシピや、市販のトッピング商品も解説。愛犬との食生活をより豊かにするちょい足しの工夫を始めてみましょう。
いつものごはんに一工夫!愛犬が喜ぶ「ちょい足し」トッピングアイデア集いつものドッグフードに飽きていませんか。愛犬の食事のマンネリを解消する、簡単なドッグフードトッピングのアイデアをご紹介します。栄養バランスを考えた手作りレシピや、市販のトッピング商品も解説。愛犬との食生活をより豊かにするちょい足しの工夫を始めてみましょう。 - ドッグフードの正しい保存方法|開封後の風味と安全を守るためのポイント正確に計量したフードも、劣化していては意味がありません。フードの品質を最後まで保つための、湿気や酸化を防ぐ正しい保存方法を解説します。
 ドッグフードの正しい保存方法|開封後の風味と安全を守るためのポイント愛犬のドッグフード、開封したら品質劣化が心配ですよね。酸化や湿気を防ぎ、フードの風味と安全性を最後まで守るための正しい保存方法を徹底解説します。保存容器の賢い選び方から、劣化しにくいフードの選び方まで、愛犬の健康を守るためのポイントがわかります。
ドッグフードの正しい保存方法|開封後の風味と安全を守るためのポイント愛犬のドッグフード、開封したら品質劣化が心配ですよね。酸化や湿気を防ぎ、フードの風味と安全性を最後まで守るための正しい保存方法を徹底解説します。保存容器の賢い選び方から、劣化しにくいフードの選び方まで、愛犬の健康を守るためのポイントがわかります。 - お腹に優しく!ドッグフードを上手に切り替えるための7日間実践ガイド計算で新しいフードに切り替えることになったら参考に。愛犬に負担をかけない、スムーズなフードの切り替えスケジュールとコツを紹介します。
 お腹に優しく!ドッグフードを上手に切り替えるための7日間実践ガイド新しいドッグフードへの切り替えで、愛犬が下痢しないか心配ですよね。このページでは、失敗しない正しい方法と期間を、7日間実践ガイドで徹底解説。子犬・老犬の注意点から、もしお腹を壊した場合の対処法まで、愛犬に負担をかけずにスムーズに切り替えるコツがすべてわかります。
お腹に優しく!ドッグフードを上手に切り替えるための7日間実践ガイド新しいドッグフードへの切り替えで、愛犬が下痢しないか心配ですよね。このページでは、失敗しない正しい方法と期間を、7日間実践ガイドで徹底解説。子犬・老犬の注意点から、もしお腹を壊した場合の対処法まで、愛犬に負担をかけずにスムーズに切り替えるコツがすべてわかります。 - ドッグフードの「ふやかし方」完全マスター!メリットと正しい手順を解説子犬やシニア犬、食欲がない時に役立つフードのふやかし方。そのメリットや、栄養を壊さない適切なお湯の温度、時間を詳しく解説します。
 ドッグフードの「ふやかし方」完全マスター!メリットと正しい手順を解説「ドッグフードのふやかし方」で、子犬やシニア犬の食事の悩みを解決したいですよね?栄養を逃さない正しい手順とお湯の温度(40℃〜50℃)、メリットを完全マスター。食いつきが悪い時の水分補給対策や、賢いフードの選び方を中立な立場から詳しく解説します。
ドッグフードの「ふやかし方」完全マスター!メリットと正しい手順を解説「ドッグフードのふやかし方」で、子犬やシニア犬の食事の悩みを解決したいですよね?栄養を逃さない正しい手順とお湯の温度(40℃〜50℃)、メリットを完全マスター。食いつきが悪い時の水分補給対策や、賢いフードの選び方を中立な立場から詳しく解説します。 - 旅行やお泊まりのドッグフードどうしてる?持ち運びの工夫と注意点愛犬との旅行やお泊まりの際のフードの準備方法。正確に計量したフードを小分けにする工夫や、品質を落とさず持ち運ぶための便利なアイテムや注意点をまとめました。
 旅行やお泊まりのドッグフードどうしてる?持ち運びの工夫と注意点旅行やお泊まりでのドッグフードの持ち運びに不安を感じていませんか?愛犬の健康を守るための小分けの工夫や、品質を落とさない保存の注意点を解説します。旅を快適にする便利グッズの選び方もわかるので、もう準備に迷うことはありませんよね?
旅行やお泊まりのドッグフードどうしてる?持ち運びの工夫と注意点旅行やお泊まりでのドッグフードの持ち運びに不安を感じていませんか?愛犬の健康を守るための小分けの工夫や、品質を落とさない保存の注意点を解説します。旅を快適にする便利グッズの選び方もわかるので、もう準備に迷うことはありませんよね?