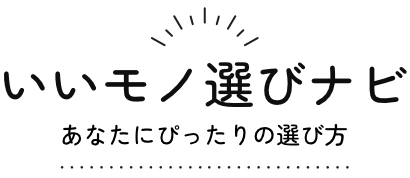はじめに:そのダイエット、間違っているかも?愛犬の体重管理を見直そう
愛犬の健康を思って、カロリーオフのダイエットフードに切り替えた。
それなのに、体重計の数字はピクリとも動かない…。
そんな経験、ありませんか。
「ちゃんとフードを選んだはずなのに、どうして痩せないの?」と、途方に暮れてしまう飼い主さんは、実はとても多いんです。
愛犬のぽっちゃり体型は、関節や心臓への負担など、様々な病気のリスクを高めてしまうと言われています。
愛犬に一日でも長く、元気にそばにいてもらうために、体重管理は飼い主としての大切な愛情表現の一つだと思います。
この記事では、なぜダイエットフードを与えているのに痩せないのか、その見落としがちな原因を詳しく解説し、ダイエットを成功に導くためのフード選びや生活習慣のコツまで、幅広くご紹介します。
この記事を読めば、愛犬のダイエットがうまくいかなかった理由が分かり、明日から何をすべきか、その具体的な道筋が見えてくるはずです。
ただし、ダイエットを始める前には、必ずかかりつけの動物病院で獣医師さんに相談してくださいね。
安全で健康的なダイエット成功への第一歩です。
「ダイエットフードなのに…」飼主さんのよくある悩み
愛犬の健康を思って、カロリーオフのダイエットフードに切り替えた。
それなのに、体重計の数字はピクリとも動かない…。
むしろ、なんだか前より食べたそうにしている気もする。
そんな経験、ありませんか。
「ちゃんとフードを選んだはずなのに、どうして痩せないの?」と、途方に暮れてしまう飼い主さんは、実はとても多いんです。
愛犬のダイエットがうまくいかないのには、フード選び以外にも、見落としがちな原因が隠れているのかもしれません。
ぽっちゃり体型のリスクとは
「うちの子、ちょっとくらいぽっちゃりしている方が可愛いし…」と思ってしまう気持ち、すごく分かります。
でも、人間と同じように、犬にとっても肥満は様々な病気のリスクを高めてしまうと言われています。
例えば、足腰の関節に負担がかかってしまったり、心臓や呼吸器に問題が出やすくなったり。
糖尿病のリスクも高まる、という話もよく耳にします。
愛犬に一日でも長く、元気にそばにいてもらうために、体重管理は飼い主としての大切な愛情表現の一つだと思います。
愛犬の「適正体重」を知っていますか?
ダイエットを始める前に、まず知っておきたいのが、愛犬の「適正体重」です。
犬種や骨格によって、理想的な体重は全く違います。
動物病院で聞くのが一番確実ですが、お家で簡単にチェックする方法もあります。
体を優しく触ってみて、肋骨(あばら骨)がうっすらと感じられるか、上から見た時に腰にくびれがあるか、などを確認してみてください。
もし肋骨が脂肪に埋もれて触れなかったり、くびれがなかったりしたら、少し体重オーバーのサインかもしれません。
小型犬
ここでご紹介するのはあくまで一般的な成犬の体重の目安です。同じ犬種でも、性別、骨格、筋肉量によって理想的な体重は異なります。
一番正確なのは、かかりつけの獣医師さんにその子の体型を診てもらい、理想の体重を教えてもらうことです。
その上で、参考として一般的な犬種の標準体重をサイズ別にいくつかご紹介しますね。
中型犬
大型犬
繰り返しになりますが、これらの数字はあくまで目安です。
ご自身の愛犬の理想体重については、動物病院で相談するのが最も確実で安心ですよ。
この記事でわかること
この記事では、なぜダイエットフードを与えているのに痩せないのか、その見落としがちな原因を詳しく解説していきます。
そして、ダイエットを成功に導くためのドッグフード選びのポイントや、食事の与え方、生活習慣のコツまで、幅広くご紹介します。
この記事を読めば、愛犬のダイエットがうまくいかなかった理由が分かり、明日から何をすべきか、その具体的な道筋が見えてくるはずです。
始める前の大切な約束:まずは獣医師に相談を
この記事では、家庭でできる体重管理のヒントをお伝えしますが、ダイエットを始める前には、必ずかかりつけの動物病院で獣医師さんに相談してください。
急激なダイエットは、かえって愛犬の健康を損なう可能性があります。
また、肥満の背景に病気が隠れていることも。
愛犬の健康状態をしっかりチェックしてもらった上で、その子に合った目標体重やペースを一緒に決めてもらうことが、安全で健康的なダイエット成功への第一歩です。
ダイエットフードでも痩せない!見落としがちな5つの原因

良かれと思ってダイエットフードに切り替えたのに、なぜか体重が減らない…。
その原因は、フードそのものではなく、私たちの「与え方」や「生活習慣」に隠されていることがほとんどです。
ここでは、ダイエットがうまくいかない時に見落としがちな5つの原因を、一緒にチェックしていきましょう。
もしかしたら、「あ、うちのことかも」と思い当たることがあるかもしれません。
原因1:与えているフードの「量」が多すぎる
ダイエットがうまくいかない原因として、実は最も多いかもしれないのが、この「量」の問題です。
飼い主さんとしては「ダイエットフードだから大丈夫」と、つい安心してしまいがちですが、どんなにカロリーが低いフードでも、食べ過ぎてしまえば当然カロリーオーバーになってしまいます。
ここに、意外な落とし穴がいくつか隠れているんです。
パッケージの給与量はあくまで目安
ダイエット成功の鍵を握るのが、食事の「量」です。
フードのパッケージの裏には、体重別に与える量の目安が書かれていますよね。
でも、あれはあくまで一般的な目安。
犬の年齢や運動量、避妊・去勢手術の有無によって、必要なカロリーは大きく変わってきます。
表の通りにあげているつもりでも、実は愛犬にとっては多すぎた、というケースは少なくありません。
「目分量」や「いつものカップ」の危険性
「だいたいこのくらいかな」と、目分量でフードをあげていませんか。
また、ドッグフード専用ではない、いつも使っているマグカップなどで計っている場合も要注意です。
その一杯が、実は推奨されている量よりもずっと多かった、なんてことも。
ほんの少しの差でも、毎日続けば大きなカロリーオーバーにつながってしまいます。
必ず、専用の計量カップを使うか、できればキッチンスケールで毎回きっちり重さを計る習慣をつけるのが、ダイエット成功への一番の近道だと思います。
理想体重から計算する必要性
もう一つ、とても大切なポイントがあります。
それは、フードの量を計算する時、今の体重ではなく、「目標とすべき理想の体重」を基準にする必要がある、ということです。
例えば、理想体重が5kgなのに、今7kgある子に、7kgの子用の量を与えていては、なかなか体重は減りませんよね。
「5kgの子だったら、これくらいの量」というのを基準に、食事の量を調整してあげる必要があります。
この計算が、ダイエットの基本中の基本になります。
原因2:フード以外の「隠れカロリー」を見逃している
毎日しっかりフードの量を計っている飼い主さんほど、陥りやすい落とし穴がこの「隠れカロリー」です。
メインの食事は完璧に管理しているつもりでも、良かれと思ってあげているおやつや、家族のちょっとした「おすそ分け」が、実はダイエットの努力を水の泡にしてしまっているかもしれません。
ここでは、そんな見過ごされがちなカロリーの侵入経路を一緒に探っていきましょう。
おやつのあげすぎ
フードの量はしっかり計っていても、おやつでカロリーオーバーになっているケースは本当に多いです。
「ほんの少しだから」と思ってあげているその一口が、体の小さな犬にとっては、私たちがケーキを一切れ食べるくらいのインパクトがあるかもしれません。
ダイエット中は、おやつはできるだけ控えるか、あげるとしても茹でた野菜や低カロリーのボーロなどに切り替え、その分のカロリーを1日の総摂取カロリーから差し引く計算が必要です。
家族がこっそりあげている
飼い主である自分は気をつけていても、「おじいちゃんがこっそりあげていた」「子供がお菓子を落としたのを食べていた」なんてことも。
愛犬の可愛いおねだり光線に、家族みんなが負けてしまっているのかもしれません。
ダイエットを成功させるには、家族全員の協力が不可欠です。
なぜダイエットが必要なのかをしっかり話し合い、「おやつは決められたもの以外あげない」というルールを、家族みんなで共有することが大切ですね。
歯磨きガムやトッピングのカロリー
見落としがちなのが、歯磨きガムや、フードの食いつきを良くするためのトッピングのカロリーです。
健康のために良かれと思ってやっていることでも、意外とカロリーが高いものは少なくありません。
特に、歯磨きガムは毎日あげる習慣があるお家も多いと思いますが、そのカロリーもきちんと把握しておく必要があります。
パッケージの裏をチェックして、そのカロリー分も考慮した上で、1日の食事量を調整してあげましょう。
原因3:選んでいるダイエットフードが合っていない
「ダイエットフード」と一言で言っても、その種類は様々です。
中には、「ライト」や「肥満傾向の成犬用」と書かれていても、思ったほどカロリーが低くないフードもあります。
また、ただカロリーが低いだけでなく、愛犬の満足感が得られるかどうかも重要です。
タンパク質が少なく、繊維質もあまり入っていないフードだと、すぐにお腹が空いてしまい、常にごはんを欲しがるようになってしまうことも。
愛犬が満足感を得ながら、健康的に痩せられるフードを選んであげることが大切だと思います。
原因4:運動不足で消費カロリーが少ない
ダイエットの基本は、「摂取カロリー < 消費カロリー」です。
食事の管理で摂取カロリーを減らすことと同時に、運動で消費カロリーを増やすことも、もちろん大切です。
食事制限だけで痩せようとすると、筋肉まで落ちてしまい、かえって痩せにくい体になってしまうことも。
お散歩の時間を少し長くしてみたり、週末はドッグランで思いっきり走らせてあげたりと、愛犬が楽しみながらできる運動を、毎日の生活に少しずつ取り入れていきたいですね。
原因5:病気が原因で体重が減りにくい可能性
食事の量も運動も気をつけているのに、どうしても体重が減らない…。
そんな時は、もしかしたら病気が隠れている可能性も考えられます。
例えば、甲状腺の機能が低下する病気(甲状腺機能低下症)など、代謝が悪くなって太りやすくなる病気もあります。
「なんだかおかしいな」と感じたら、自己判断で無理な食事制限などを続けるのではなく、必ず動物病院で相談してください。
ダイエットを始める前の健康診断が、やはりとても重要だということですね。
愛犬のダイエットを成功に導く!ドッグフード選びの5つのポイント

ダイエットがうまくいかない原因がわかったら、次はいよいよフード選びの見直しです。
「ダイエットフード」と名のつく商品はたくさんありますが、ただカロリーが低ければ良い、というわけではありません。
愛犬の健康を維持しながら、満足感も得られるようなフードを選んであげることが、ダイエット成功の秘訣です。
ここでは、ダイエット用のドッグフードを選ぶ際に、チェックしたい5つの大切なポイントをご紹介します。
ポイント1:「低脂肪・低カロリー」の数値を確認する
まず基本となるのが、フードの脂質とカロリーです。
ダイエット用のフードは、一般的な成犬用フードに比べて、脂質やカロリーが低く調整されています。
パッケージの成分表示欄にある「粗脂肪」のパーセンテージや、「代謝エネルギー(ME)」と書かれているカロリーの数値をチェックしてみましょう。
「〇〇%オフ」といった表記だけでなく、具体的な数字を見て、今あげているフードと比べてどれくらい低いのかを確認する習慣をつけると、フード選びの精度が上がると思います。
ただし、極端に低すぎるフードは、必要な栄養素まで不足してしまう可能性があるので注意が必要ですね。
ポイント2:「高タンパク質」で筋肉量を維持する
ダイエット中に気をつけたいのが、「筋肉が落ちてしまうこと」です。
食事制限をすると、脂肪だけでなく筋肉も一緒に落ちてしまいがち。
筋肉量が減ると、基礎代謝も下がってしまい、かえって痩せにくく、リバウンドしやすい体になってしまうと言われています。
そうならないためにも、良質なタンパク質をしっかり摂って、筋肉量を維持することがとても大切です。
ダイエットフードを選ぶ際は、低カロリーでありながら、「高タンパク質」な設計になっているフードを選ぶのがおすすめです。
鶏肉や魚など、消化しやすく脂肪の少ないタンパク質が主原料になっているものが良いと思います。
ポイント3:「高繊維質」で満腹感を持続させる
ダイエット中の愛犬にとって、一番の敵は「空腹感」かもしれません。
いつもお腹を空かせていては、愛犬も辛いですし、飼い主さんもおねだりに負けてしまいそうになりますよね。
そこでおすすめなのが、食物繊維が豊富に含まれているフードです。
食物繊維は、お腹の中で水分を吸って膨らむ性質があるため、少ない量でも満腹感を得やすく、腹持ちが良いと言われています。
また、便通を良くする効果も期待できるので、ダイエット中のウンチの悩みをサポートしてくれることも。
原材料に、野菜や豆類、海藻などが使われているかチェックしてみてください。
ポイント4:皮膚や関節の健康をサポートする成分
体重が増えると、皮膚や関節にかかる負担も大きくなります。
ダイエット中は、食事量が減ることで、皮膚の健康に必要な栄養素が不足し、毛並みがパサパサになってしまうことも。
また、運動を頑張る子の関節ケアも気になりますよね。
そのため、皮膚の健康を保つオメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸、関節の健康をサポートするグルコサミンやコンドロイチンといった成分が配合されているフードを選ぶと、より安心してダイエットに取り組めると思います。
健康的に美しく痩せる、というのが理想ですね。
ポイント5:食いつきが良いことも大切
どんなに栄養バランスが優れたダイエットフードでも、愛犬が食べてくれなければ意味がありません。
ダイエット中はただでさえ食事量が減るので、毎日のごはんが楽しみになるような、美味しいフードを選んであげたいものです。
カロリーを抑えるために、嗜好性が落ちてしまうフードも中にはあるようです。
口コミを参考にしたり、少量のお試しパックがあるフードから試してみたりするのも良い方法です。
我慢ばかりのダイエットではなく、愛犬が喜んで食べてくれるフードを見つけて、楽しく続けていくことが、成功への一番の近道だと思います。
食事だけじゃない!体重管理を成功させる5つの生活習慣
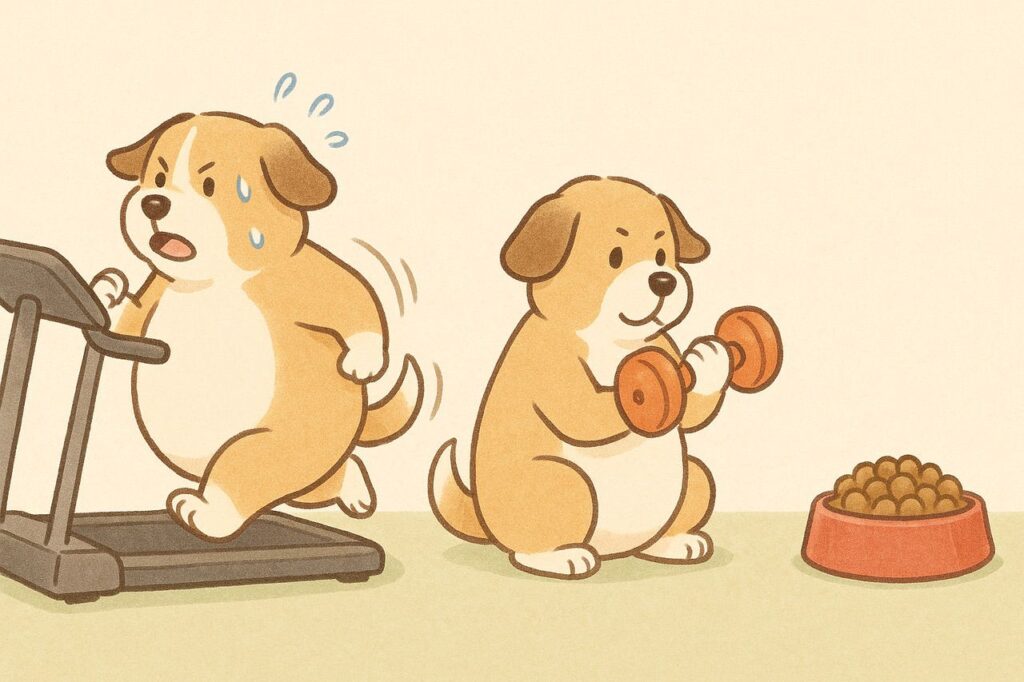
愛犬にぴったりのダイエットフードが見つかったら、ダイエットは半分成功したようなものです。
でも、残りの半分を成功させるためには、フード以外の「生活習慣」を見直すことも、同じくらい大切になってきます。
食事の管理と生活習慣の改善は、ダイエットの両輪のようなもの。
ここでは、愛犬のダイエットをサポートし、リバウンドを防ぐために、毎日の生活に取り入れたい5つの習慣をご紹介します。
少しの工夫で、ダイエットの効率がぐっと上がるかもしれませんよ。
習慣1:食事の与え方を工夫して満足度アップ
ダイエット中は食事の量が減ってしまうため、愛犬が「まだ食べたいよー」と物足りなそうな顔をしていると、胸が痛みますよね。
ですが、与え方を少し工夫するだけで、同じ量のフードでも満足感を大きくアップさせることができます。
ここでは、愛犬のお腹と心を満たす、ちょっとした食事のテクニックをご紹介します。
食事回数を増やす
ダイエット中は食事の量が減るため、どうしてもお腹が空きやすくなります。
そんな時は、1日のフードの総量は変えずに、食事の回数を2回から3回、4回へと増やしてあげるのがおすすめです。
一度に食べる量は減りますが、食事の回数が増えることで、空腹でいる時間が短くなり、愛犬の満足度が上がると言われています。
「まだかな?」とごはんを待つストレスも、和らげてあげられるかもしれませんね。
早食い防止食器を使う
ガツガツと一瞬でごはんを食べ終えてしまうと、満腹感を得にくく、「もう食べちゃったの?」と物足りなさを感じてしまうことがあります。
そんな早食い気味の子には、内側に凹凸がついた早食い防止用の食器を使ってみましょう。
食べるのに時間がかかるようになるので、ゆっくり味わって食べる習慣がつき、少ない量でも満足感を得やすくなる効果が期待できます。
フードをふやかしてカサ増しする
ドライフードをぬるま湯でふやかしてあげるのも、とても良い方法です。
フードが水分を吸って膨らむので、見た目のボリュームが増し、満足感アップに繋がります。
消化にも優しくなりますし、同時に水分補給もできるので、一石二鳥ですね。
ダイエット中の便秘対策としても、効果が期待できると思います。
習慣2:おやつのルールを家族で共有する
ダイエットが失敗する一番の原因と言っても過言ではないのが、「おやつ」です。
自分はあげていなくても、他の家族がこっそりあげていた…なんてことは、本当によくある話。
ダイエットを成功させるには、家族全員の協力が不可欠です。
「なぜこの子にダイエットが必要なのか」「おやつをあげすぎるとどんなリスクがあるのか」を家族みんなで話し合い、「おやつは1日にこれだけ」「この時間以外はあげない」といったルールを決め、全員で守るようにしましょう。
おやつカウンターのようなものを作って、あげた量を記録するのも良い方法かもしれません。
習慣3:毎日の運動を楽しみながら続ける
健康的に痩せるためには、食事管理と合わせて、適度な運動で消費カロリーを増やすことが大切です。
無理に長距離を歩かせる必要はありません。
まずは、いつものお散歩のコースを少しだけ長くしてみたり、坂道や階段をコースに取り入れてみたりするだけでも、良い運動になります。
お家の中でも、ボール投げや引っ張りっこなどの遊びを積極的に取り入れて、愛犬が「楽しい!」と感じながら体を動かせる時間を作ってあげましょう。
飼い主さんとのコミュニケーションも深まり、ストレス解消にも繋がるはずです。
習慣4:定期的に体重と体型をチェックする
ダイエットのモチベーションを保つために、定期的な体重測定はとても重要です。
毎週1回、同じ曜日の同じ時間帯に体重を計るなど、ルールを決めて記録をつけていきましょう。
動物病院やペットショップの体重計を利用するのも良いですね。
ただし、数字だけにとらわれすぎないことも大切です。
体重と合わせて、体のラインもチェックしましょう。
定期的に愛犬の体を撫でて、肋骨の触れ具合やくびれの深さを確認したり、写真を撮って見比べたりするのもおすすめです。
少しの変化でも、飼い主さんが気づいて褒めてあげることが、ダイエット継続の励みになります。
習慣5:ストレスケアを忘れない
食事の量が減ったり、大好きなおやつを制限されたりすることは、犬にとってもストレスになることがあります。
ストレスを感じると、かえって食欲が増してしまったり、問題行動に繋がったりすることも。
ダイエット中は、今まで以上に愛犬とのコミュニケーションを大切にし、たくさん褒めて、たくさん遊んであげる時間を作ってあげてください。
ブラッシングやマッサージなどのスキンシップも、愛犬をリラックスさせるのにとても効果的です。
「ダイエットを頑張ってくれてありがとう」という気持ちを伝え、心を満たしてあげることが、ダイエット成功の隠れたコツだと思います。
【参考】ダイエットにおすすめのプレミアムドッグフードとは?

ダイエットフード選びの5つのポイントをご紹介しましたが、「その条件を全部満たすフードって、探すのが大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。
そんな時に、フード選びの候補として知っておくと便利なのが、原材料や栄養バランスにこだわって作られた「プレミアムドッグフード」です。
なぜプレミアムフードがダイエットに向いているの?
プレミアムドッグフードが、ダイエット中の子におすすめされるのには、ちゃんとした理由があります。
それは、これまでお話ししてきた「低脂肪・低カロリーなのに高タンパク質」「満腹感をサポートする良質な繊維質」「筋肉や関節をケアする成分配合」といった、健康的なダイエットで重視したいポイントをクリアしている商品が多いからです。
ただ体重を落とすだけでなく、筋肉量を維持し、愛犬の満足感や健康にも配慮して作られているため、リバウンドしにくい、理想的な体型を目指しやすいと言えるかもしれませんね。
ダイエットで評価の高いフードの例
「具体的にどんなフードがあるの?」と気になりますよね。
ダイエットに励む多くの飼い主さんから、「これを試したら健康的に体重管理ができた」という声が聞かれるフードを、参考までにいくつかご紹介します。
- モグワン
主原料にチキンとサーモンを使用し、良質なタンパク質をしっかり摂れるのが特徴です。
グレインフリー(穀物不使用)で、野菜やフルーツもバランス良く配合されているため、満足感を得ながら健康的にダイエットを進めたい場合に、よく選ばれているフードの一つです。 - カナガン
こちらもチキンをたっぷり使ったグレインフリーのフードです。
犬の体に負担をかけにくいサツマイモなどを炭水化物源として使用し、しっかりとした食べ応えがあるのが特徴です。
筋肉量を維持しながら、ヘルシーに体重管理をしたいと考える飼い主さんに人気があります。
大切なのは「愛犬に合うか」を見極めること
いくつか具体的なフードを挙げましたが、一番大切なことをお伝えします。
それは、どんなに評判が良いフードでも、「最終的に、あなたの愛犬の体に合うかどうかが全て」だということです。
フードを切り替えた後は、体重の変化はもちろん、ウンチの状態や毛並み、元気があるかなどをしっかり観察してあげてください。
愛犬が喜んで食べてくれて、なおかつ健康的に体重が管理できる、その子にとってのベストなフードを見つけてあげることが、ダイエット成功の一番の秘訣だと思います。
まとめ:正しい知識で、愛犬と楽しく健康的なダイエットを続けよう

今回は、ダイエットフードを与えているのになかなか痩せない、という飼い主さんの悩みに焦点を当てて、その原因から具体的な対策までを詳しくお話ししてきました。
愛犬のダイエットがうまくいかない原因は、フードの「量」の計り間違いや、おやつなどの「隠れカロリー」、そして運動不足など、意外なところに見落としがあることが多いです。
ダイエットを成功させるためのフード選びでは、
- 「低脂肪・低カロリー」であること
- 筋肉を維持する「高タンパク質」であること
- 満腹感を得やすい「高繊維質」であること
- 健康をサポートする成分が入っていること
- 愛犬が喜んで食べてくれること
この5つのポイントを意識してみてください。
そして何より大切なのは、食事管理だけでなく、運動や家族とのルール共有、ストレスケアといった「生活習慣」全体で、愛犬のダイエットをサポートしてあげることです。
ダイエットは、愛犬にとっても飼い主さんにとっても、決して楽な道のりではないかもしれません。
でも、正しい知識を持って、焦らず、楽しみながら続けることができれば、きっと良い結果に繋がるはずです。
この記事を参考に、愛犬との健康的でハッピーな毎日を目指して、今日からできることを見直してみてはいかがでしょうか。