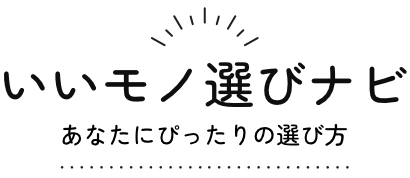はじめに:愛犬がドッグフードを食べてくれない…その悩み、解決できるかもしれません
「あれ、昨日まであんなにガツガツ食べてたのに…」
愛犬が急にごはんを残したり、そっぽを向いたりすると、すっごく心配になりますよね。
「どこか具合でも悪いのかな?」「このドッグフード、もう飽きちゃった?」なんて、頭の中がハテナでいっぱいになる気持ち、私もよーくわかります。
でも、新しいフードをポチる前に、ちょっと待ってください!
もしかしたら、そのお悩み、いつものフードを変えずに、ほんの少しの工夫で解決できるかもしれませんよ。
この記事では、まず「どうして愛犬がドッグフードを食べなくなってしまうのか」という理由を一緒に探り、そのうえで、今日からすぐに試せる「食いつきをアップさせる5つの工夫」を具体的にお伝えしていきます。
この記事を読み終わる頃には、きっと「なるほど、これなら試せるかも!」と、少し肩の力が抜けて、前向きな気持ちになっているはず。
あなたと愛犬のごはんタイムが、もっと楽しくてハッピーな時間になるためのお手伝いができたら嬉しいです。
まずは原因を探ろう。犬がドッグフードを食べない4つの理由

工夫を試す前に、まずは「どうして食べてくれないんだろう?」と、愛犬の気持ちになって原因を考えてみることが大切です。
理由は一つじゃないかもしれませんが、主な原因として考えられる4つのパターンを見ていきましょう。
理由1:わがまま・偏食?「もっと美味しいもの」を待っている
食卓からお肉をポロリ、なんて経験ありませんか?
一度でも美味しいおやつや人間の食べ物の味を覚えてしまうと、「いつものフードより、もっと美味しいものが出てくるはず!」と、ごはんを待つようになっちゃう子がいます。
これは犬が賢い証拠でもありますが、飼い主さんとしてはちょっと困りものですよね。
愛犬のキラキラした瞳に負けて、つい何かあげてしまう…その優しさが、意図せず偏食を育ててしまっているのかもしれません。
理由2:いつものフードに飽きた・好みの味ではない
私たち人間も、毎日同じメニューだと「たまには違うものが食べたいな」って思いますよね。実は、ワンコも同じなんです。
ずっとお気に入りだったフードでも、ある日突然プイッとそっぽを向くのは、「飽きちゃったよ〜」というサインなのかも。
また、フードの匂いや、粒の硬さ・大きさといった食感が、そもそもその子の好みではない可能性も考えられます。
理由3:ストレスや環境の変化が食欲に影響している
犬はとってもデリケートな生き物。引っ越しや模様替え、家族が増えたり減ったり、お留守番の時間が長くなった…など、私たちにとっては些細なことでも、彼らにとっては大きな環境の変化。
そういったストレスが、食欲不振という形で体に現れることがあります。
「最近、何か環境が変わったことはなかったかな?」と、愛犬の周りの出来事を振り返ってみるのも一つのヒントになります。
理由4:体調不良や病気のサインかも
一番気をつけてあげたいのが、このパターンです。食欲がないのは、もしかしたら体のどこかが痛かったり、具合が悪かったりするサインかもしれません。
「ごはんを食べない」以外に、「いつもより元気がない」「下痢や嘔吐をしている」「水をたくさん飲む」といった、普段と違う様子が見られないか、よく観察してあげてください。
※少しでも「あれ?」と思うことがあれば、自己判断せずに、まずはかかりつけの動物病院に相談してくださいね。 何かあってからでは遅いので、プロの目で診てもらうのが一番安心です。
フードを変えずに試せる!愛犬の「食いつき」を良くする5つの工夫

愛犬がごはんを食べない原因、なんとなく見えてきたでしょうか?
体調に問題がないことがわかったら、いよいよ実践編です!
ここでは、今あるドッグフードを買い替えることなく、すぐに試せる食いつきアップの工夫を5つご紹介します。
工夫1:フードを人肌に温めて「香り」を立たせる
犬は人間よりもずっと嗅覚が優れている動物。だから、食事の「香り」は食欲を刺激する一番のスイッチなんです。
ドライフードを電子レンジでほんの数秒(5〜10秒くらい)温めて、人肌くらいの温度にしてあげてみてください。
フワ〜っとフードの香りが立つことで、「お、なんだか美味しそうな匂いがするぞ?」と愛犬の興味を引くことができます。
お湯でふやかしてあげるのも良い方法ですよ。ただし、熱すぎるとヤケドの原因になるので、必ず飼い主さんが温度を確認してからあげてくださいね。
工夫2:いつものフードに「ちょい足し」トッピング
毎日同じごはんで飽きている様子のときは、この「ちょい足し」作戦が効果的です。
茹でて細かくした鶏ささみや、風味の良い犬用のふりかけ、匂いの強いウェットフードなどをほんの少しだけ混ぜてあげると、食欲がグンとアップすることがあります。
他にも、茹でて刻んだキャベツやニンジンなどの野菜や、無糖のヨーグルトも人気のトッピングです。
ただし、あくまで主役はドッグフード。トッピングのあげすぎは栄養バランスの偏りや、さらなる偏食につながるので、「香り付け」程度の少量に留めるのがポイントです。
工夫3:フードの「食感」を変えてみる
カリカリのドライフードが苦手な子もいます。そんなときは、ぬるま湯でフードをふやかして、柔らかくしてあげましょう。
ウェットフードのような食感になり、食べやすさが格段にアップします。特に、歯が弱い子犬やシニア犬にはおすすめの方法です。
逆に、フードの粒が大きくて食べにくそうにしている場合は、少し砕いて小粒にしてあげるのも良いでしょう。ほんのひと手間で、愛犬にとっての「食べやすさ」が大きく変わるかもしれません。
工夫4:コミュニケーションで「食事は楽しい時間」に
ごはんの時間に、飼い主さんがそばにいて優しく声をかけてあげるだけでも、犬は安心して食事をすることができます。
「美味しいね」「上手だね」と見守ってあげたり、時にはフードを手から一粒ずつあげてみたり。
そして、食べ終わったら「全部食べられて偉かったね!」と思いっきり褒めてあげましょう。
こういったコミュニケーションを通じて、「ごはんの時間は、飼い主さんと触れ合える嬉しい時間なんだ」と学習してくれれば、食事へのモチベーションも自然と上がっていきます。
工夫5:おやつのルールを見直す
意外と見落としがちなのが、おやつの存在。
可愛い愛犬にねだられると、ついついあげたくなっちゃいますよね。
でも、おやつの量やタイミングによっては、それだけでお腹がいっぱいになってしまい、肝心なごはんが食べられなくなっているケースがよくあります。
「ごはんの前にあげない」「一日の量をしっかり決める」など、おやつのルールを一度見直してみましょう。
しつけのご褒美として、いつものドッグフードを一粒あげるようにするのも、フードへの関心を高める良い方法ですよ。
意外な盲点?食事の環境も見直してみよう

フードにトッピングをしたり、温めたりと色々工夫しても、なかなか食いつきが改善しない…。
そんな時は、一度フードそのものから視点を変えて、「食事をする環境」を見直してみませんか?
私たち人間も、騒がしい場所や食べにくいテーブルでは、せっかくのごはんも美味しく感じられませんよね。
それは犬も同じ。意外と見落としがちな食事の環境が、愛犬の食欲を左右しているのかもしれません。
食器は愛犬に合ってる?高さや素材をチェック
毎日使っているその食器、もしかしたら愛犬にとっては「食べにくい」ものなのかも。
例えば、食器の位置が低すぎると、首をぐっと下げないといけないので、特にシニア犬や体の大きな犬には負担になることがあります。
そんな時は、高さのあるフードスタンドを使ってあげると、楽な姿勢で食べられるようになりますよ。
また、食器の素材もポイントです。
軽いプラスチック製の食器は、傷がつきやすく、その傷に雑菌が繁殖したり、フードの油分が残って匂いの原因になったりすることも。
匂いに敏感な子だと、それが気になって食べないケースもあります。
お手入れがしやすく衛生的な、陶器やステンレス製の食器に変えてみるのも一つの手です。
食事場所は安心できる?騒がしい場所は避ける
犬にとって、食事の時間は無防備になる時間。周りを気にせず、安心してごはんに集中できる場所を用意してあげることは、とても大切です。
家族が頻繁に通る廊下や、テレビや洗濯機の音が大きく響く場所は、落ち着かないので食事には不向きです。
できるだけ静かで、人があまり通らないお部屋の隅っこなどを、愛犬専用の食事スペースにしてあげると良いでしょう。
「ここは僕・私のレストランだ」と安心して、リラックスしてごはんを楽しめるはずです。
他の犬や家族からのプレッシャーはない?
多頭飼いのおうちで特に気をつけたいのが、他の犬からのプレッシャーです。
仲良しに見えても、犬には「自分のごはんは自分で守る」という本能があります。
他の犬が近くにいるだけで、「取られちゃうかも…」と気になってしまい、食べることに集中できない子がいます。
そんな場合は、犬同士の距離を離してあげたり、部屋を分けたり、ケージの中でそれぞれ食べさせたりと、お互いの存在が気にならないように工夫してあげましょう。
また、犬だけでなく、ごはんを食べている時に小さなお子さんがちょっかいを出したり、じーっと見つめたりするのも、犬にとってはプレッシャーになることがあるので、そっと見守ってあげるようにしたいですね。
これはNG!ドッグフードを食べない時にやってはいけないこと

愛犬にごはんを食べてほしい一心で、ついついやってしまいがちな行動が、実は逆効果になっていることもあります。
ここでは、良かれと思ってやったことが裏目に出ないように、避けるべき3つのNG行動をお伝えします。
NG行動1:叱ったり無理やり食べさせるのは逆効果
「どうして食べないの!」と強い口調で叱ったり、無理やり口にフードを押し込んだりするのは絶対にやめましょう。
犬からすると、大好きな飼い主さんに怒られる「嫌な時間」になってしまい、ますます食事が嫌いになるという悪循環に陥ってしまいます。
飼い主さんの「食べてほしい」という焦る気持ちは、賢い愛犬にはちゃんと伝わっています。
まずは私たちがリラックスして、「食べなくても大丈夫だよ」くらいの大きな気持ちで接してあげることが大切です。
NG行動2:「置き餌」は食への興味を失わせる原因に
いつでも食べられるようにと、フードボウルに一日中フードを入れっぱなしにする「置き餌」。
一見、親切なように見えますが、これもあまりおすすめできません。
いつでも食べられる環境は、食事のありがたみや「決まった時間にごはんがもらえる」という楽しみを奪ってしまい、かえって食への興味を失わせてしまうことがあります。
また、フードが長時間空気に触れることで風味が落ちたり、夏場は雑菌が繁殖したりと、衛生面でも心配です。
食事の時間はきっちり決めて、食べなかったら一度片付ける、というメリハリをつけましょう。
NG行動3:安易に人間の食べ物を与えるのは避ける
フードを食べないからといって、「じゃあ、代わりにこれを…」と人間の食べ物を与えてしまうのは、最も避けたい行動です。
一度味の濃い美味しいものを覚えてしまうと、ますますドッグフードを食べなくなり、偏食をどんどん助長させてしまいます。
それだけでなく、玉ねぎやチョコレートのように犬にとって中毒を引き起こす危険な食材を与えてしまうリスクもあります。
犬にとっては塩分や糖分、脂肪分が多すぎることも多く、将来の健康問題につながる可能性もあるので、人間の食べ物は安易に与えないようにしましょう。
【Q&A】ドッグフードを食べない悩み、よくある質問
ここまで色々な工夫や原因についてお話ししてきましたが、それでもまだ「こういう時はどうしたらいいの?」と疑問に思うこともありますよね。
ここでは、飼い主さんからよく寄せられる質問にQ&A形式でお答えしていきます。
Q. 食べなかったフードは、すぐに片付けた方がいい?
A. はい、15分から30分くらいを目安に片付けるのがおすすめです。
「置き餌」のセクションでも少し触れましたが、食べないからといってフードを出しっぱなしにしておくと、「いつでも食べられるや」と学習してしまい、食事のメリハリがなくなってしまいます。
「この時間内に食べないと、ごはんはなくなっちゃうんだ」と覚えてもらうためにも、決めた時間になったら「ごちそうさま」と声をかけて、食器を下げてしまいましょう。
最初はかわいそうに思うかもしれませんが、このメリハリが次の食事への意欲につながります。
Q. いろいろ試してもダメ…フードを切り替えるタイミングは?
A. まずは体調に問題がないことが大前提です。
その上で、今回ご紹介したような工夫や環境の見直しを試しても、どうしても食べてくれない日が続くようであれば、フードの切り替えを検討するタイミングかもしれません。
フードを切り替える際は、今のフードの何が気に入らないのか(匂い?粒の大きさ?味?)を考えて、次は違うタイプのものを選んでみると良いでしょう。
そして、新しいフードに変える時は、一気に全部を切り替えるのではなく、今までのフードに少しずつ混ぜながら、1週間から10日ほどかけてゆっくり慣らしてあげるのが、お腹に負担をかけないコツですよ。
Q. トッピングは毎日あげても大丈夫?
A. 栄養バランスが崩れない程度の「ごく少量」であれば、毎日あげても基本的には問題ありません。
ただし、注意したいのは、トッピングが当たり前になって「トッピングがないと食べない!」という、さらなる偏食っ子に育ててしまう可能性があることです。
トッピングはあくまで食欲を刺激するための「ふりかけ」のようなもの。
頼りすぎず、日によってトッピングを変えてみたり、時にはトッピングなしで食べられたらたくさん褒めてあげたりと、上手に活用していくのが良い付き合い方です。
まとめ:焦らず、愛犬に合った工夫で「食べない」を解決しよう
今回は、愛犬がドッグフードを食べない原因と、今日からすぐに試せる5つの工夫についてお話ししてきました。
愛犬がごはんを食べてくれない理由は、単純な偏食や飽きだけでなく、環境の変化によるストレスや、もしかしたら体調不良のサインである可能性まで、本当に様々です。
まずは「もしかして病気かも?」という視点を忘れずに、愛犬の様子をよく観察してあげてください。その上で、体調に問題がなさそうであれば、今回ご紹介した
- フードを温めて香りを立たせる
- ほんの少しだけトッピングする
- フードの食感を変えてみる
- 食事の時間を楽しいものにする
- おやつのルールを見直す
といった工夫を、一つずつ試してみてはいかがでしょうか。
大切なのは、飼い主である私たちが焦らないこと。
「食べてくれない…」と不安になる気持ちも分かりますが、その気持ちは愛犬にも伝わってしまいます。
「まあ、今日食べなくても明日食べてくれるか!」くらいの、ゆったりとした気持ちで向き合ってみてください。
この記事が、あなたと愛犬の食事が、もっと楽しくて幸せな時間になるためのヒントになれば嬉しいです。
【参考】最後の手段?プレミアムドッグフードという選択肢

色々な工夫を試してみたけれど、どうしても愛犬がごはんを食べてくれない…。
そんな時の「最後の手段」として、最近よく耳にする「プレミアムドッグフード」という選択肢があります。
これは一体どんなフードで、いつものフードと何が違うのでしょうか。参考情報として、少しだけご紹介しますね。
そもそも「プレミアムドッグフード」って何が違うの?
実は、「プレミアムドッグフード」という言葉に、法律で定められたような明確な定義はありません。
一般的には、原材料や製法にこだわって作られた、ちょっとリッチなドッグフードのことを指します。
例えば、新鮮なお肉やお魚を主原料にしていたり、人工的な着色料や保存料といった添加物を使っていなかったりするのが特徴です。
中には、私たち人間が食べられる品質の食材を使った「ヒューマングレード」や、アレルギーに配慮してトウモロコシや小麦などの穀物を使わない「グレインフリー」といったタイプもあります。
メリットとデメリットを知っておこう
そんなプレミアムドッグフードですが、もちろん良い点ばかりではありません。
メリットとデメリットを簡単にまとめてみました。
- メリット
- 食いつきが良い傾向がある:高品質なお肉やお魚をたっぷり使っているものが多く、犬が好む自然な香りと味わいが、食欲をそそりやすいと言われています。
- 毛並みやウンチの状態に変化が期待できる:良質な栄養を摂ることで、体の内側から健康をサポートし、毛並みが良くなったり、ウンチの匂いや状態が改善されたりすることがあります。
- デメリット
- 価格が高い:こだわりの原材料を使っている分、一般的なフードに比べて価格は高くなる傾向があります。
- 手に入りにくい場合がある:スーパーやホームセンターではあまり見かけず、ペット用品の専門店やインターネット通販での購入がメインになることが多いです。
【具体例】食いつきの良さで人気のプレミアムドッグフード
「プレミアムフードって色々あるけど、具体的にどんなもの?」と気になりますよね。
ここでは、特に「食いつきの良さ」で多くの飼い主さんから支持されているフードを2つ、例としてご紹介します。
フード選びの参考にしてみてください。
- モグワンドッグフード チキンとサーモンをたっぷり50%以上も使っていて、袋を開けた瞬間に、お魚系のとても良い香りがするのが特徴です。
この香りに誘われて、今まで食が細かった子も喜んで食べるようになった、という声もよく聞きます。もちろん、グレインフリー(穀物不使用)で、野菜やフルーツもバランス良く配合されています。 - カナガンドッグフード こちらもグレインフリーで、上質なチキンを主原料にしています。
「犬が本来必要とする食事」をコンセプトに、犬の体に負担がかかりやすい穀物を使わず、代わりに栄養価の高いサツマイモや豆類を使用。
チキンの旨味が凝縮されているので、特にお肉好きなワンちゃんの食いつきが期待できます。
どんな場合に検討する価値がある?
では、どんな時にプレミアムドッグフードを検討してみると良いのでしょうか。
例えば、愛犬が特定の食物アレルギーに悩んでいる場合や、今回ご紹介した様々な工夫を試しても、どうしても食いつきが改善しない場合の「最終手段」として考えてみるのは一つの手です。
もちろん、すべての犬にプレミアムドッグフードが必要なわけではありません。大切なのは、価格や評判だけで選ぶのではなく、そのフードが本当に自分の愛犬に合っているかどうかです。
もし興味があれば、まずは少量のお試しパックなどから始めてみるのも良いかもしれませんね。あくまで選択肢の一つとして、頭の片隅に置いておくと、フード選びの幅が広がるかもしれません。